ナビ8 
[注] レイアウトがくずれることがあります。ご了解ください。
2014(平成26)年
2月26日(水)
本ホームページのナビ1「心を楽にする考え方」に加筆をし再構成して、昨日更新しました。古いパソコンとスマートフォンでは更新されていて見られるのですが、新しいパソコンで見ると更新されていません。
下記2月7日に書いたようにナビ6「細山敏之のプロフィール」に第8回『「進化する密教(仏教)」と「アートセラピー」』の更新は古いパソコンでインターネットを通して見られても、新しいパソコンやスマートフォンで見ると更新されていない。
今回はスマートフォンでは見られる!
原因がパソコン、ソフト、使い方などのどれにあるのかは、まだわかりません。
現在、予定を変更して、ナビ5『「心の5段階説」と「心の10段階説」』を更新しようとして作業をしています。
今後、順次、各ページを修正し更新していく予定です。
すべてで見られるようになるといいのですが……。
トップページに戻る
2月7日(金)
本ホームページのナビ6「細山敏之のプロフィール」に第8回「進化する密教(仏教)」と「アートセラピー」について書き、一昨日更新しました。しかし、本HPをつくるために使っている古いパソコンでインターネットを通してみると更新されているのですが、新しいパソコンやスマートフォンで見ると更新されていません。不思議な現象ですが、原因はわかりません。
現在、更新できない文書はナビ6のものだけなので、とりあえず下記にコピーしました。一部、本日記の1月23日とダブりますが、そのままにさせていただきました。
トップページに戻る
第8回 「進化する密教(仏教)」と「アートセラピー」 [2014.2.5]
久しぶりにホンモノの両界曼荼羅と立体曼荼羅を見たいと思い「空海と密教美術展」(東京国立博物館、2011.9.14)へ行ったとき、一番大きな曼荼羅が片方ずつしか展示されていなかったこと(傷がついたためor劣化を防ぐためor見所を分けるため?)と、立体曼荼羅の中心に一番大切な大日如来がない展示だったことに、正直なところがっかリして、自分なりに密教と美術の魅力、意義などを人々へ伝えるお役に立ちたいと思い、当時決まっていた予定を変更させていただき、取り組みはじめた。ただし、単行本をつくるのではなく、絵を1枚ずつつくり、最終的に新しいシンプルな曼荼羅をつくってみたいと思った。
まず胎蔵界と金剛界(両界)の大日如来の絵をマンガ家の石田おさむさんへ依頼した。曼荼羅にはたくさんの仏が描かれているが、人々に親しまれてきた重要な仏を絵にしたいと思い、次に釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来を依頼した。
昨年3月に大阪の四天王寺で天台密教系最古といわれる両界曼荼羅をみたことを機に、弘法大師空海によって完成された真言密教に対して、伝教大師最澄の弟子の円仁、円珍、安然らが「顕密一如」(密教以外が顕教)という教義、理論を確立し天台密教を完成したことを知った。その意義はまだあまり一般の人々には知られていないし、その成果も現代にいたるまで生かされていないように思われた。しかし、今後、未来において非常に意義、意味があるように感じた。
新しい組み合わせの二尊像や三尊像の絵をつくっていたときであるので、「顕密一如」の考え方は理論的な裏づけをしてくれているように思われた。そして絵は、その理論・教義を広めることにも役立つのではないかと思った。
釈迦から始まった仏教の歴史を考えると、仏教は分化しながら進化してきたともいえる。また密教も進化してきていることから、「進化する仏教」「進化する密教」という視点から、経典や伝統の重要性を尊重しつつも、経典や伝統などにとらわれすぎずにアートとして創作させていただいている。
密教や仏教が発展し進化してきた一方で、弊害としては自分の宗派、教義のみが尊いとする指導者がでてきたことから、宗派・宗教の対立が生じやすくなったことである。「顕密一如」の考え方は「自分だけでなく他者も尊い」ということで、宗派・宗教の対立を防ぐ意義がある。そのためにも各宗派のよさを生かしながら統合していく試みがあってもいいように思わる。統合をするためにも絵が役立つのではと思い始めている。
それに優るとも劣らず重要なのは、個人の心身を明るく元気にして生きることや、精神的な成長、心身の統合にも役立つ絵になることであろう。
近年「アートセラピー」、芸術療法などが発展してきている。絵を描いたり創作することを通して、心のトラウマ、原因を探りながら、心の成長をはかり、心の病を治していく方法である。
仏画や仏像などの絵画や彫刻などは人の心を広げて深める効果がある。筆者らがつくる絵が広い意味での「アートセラピー」に役立てばと思っている。広い意味での「アートセラピー」とは、正しくいうと「アート鑑賞セラピー」といえるであろう。つまり、絵を見ることによって心の成長ができ、心の病が治るきっかけが得られることである。ただし、絵に感動して瞬時に治る場合もあるかもしれないが、一般的にはそれなりの時間が必要であろう。
「アート鑑賞セラピー」については、本ホームページで別の項目を設けて説明をしたいと思っている。
美と光が感じられる絵がやっと完成したので、多くの人々にみて活用していただきたいと思い、誰でもが無料で掲載できる手作りマーケットサイト「テトテ」に先日載せさせていただいた。
マンガ家の石田おさむさんとのコラボレイションによる作品は、「胎蔵界の大日如来 慈悲」「金剛界の大日如来 知恵」「釈迦如来 抜苦与楽」「薬師如来 心身治癒」「阿弥陀如来 極楽往生」(各々リンクしていますので、クリックするとみられます)です。
近々、上記の五如来の二尊像、三尊像を載せたいと思っている。現在は5体の菩薩に取り組んでもらっています。
また、イラストレーターの北村卓士さんとのコラボレイションによる作品は、「七福神 宝船と大宝塔」「七福神とダイヤモンド富士」である。
いずれもコラボレイションによる作品であることから、「コラボレイターズ」というニックネームで登録、公開させていただいた。
ご覧をいただき、ご活用をしていただければ幸いです。
トップページに戻る ナビ6「細山敏之のプロフィール」へ
1月23日(木)
クリエイターが無料で作品を展示、販売できる「dクリエイターズ」「テトテ」について下記(元旦)に書きましたが、思っていた以上に時間がかかっています。手続きが先に進んだ「テトテ」にやっと載せることができ始めました。
マンガ家の石田おさむさんとコラボレイションをした「胎蔵界の大日如来 慈悲」「金剛界の大日如来 知恵」「釈迦如来 抜苦与楽」「薬師如来 心身治癒」「阿弥陀如来 極楽往生」、イラストレイター北村卓士さんとの「七福神 宝船と大宝塔」「七福神とダイヤモンド富士」です(それぞれリンクしましたのでクリックしてご覧ください)。
「進化する密教(仏教)」という視点から創作して、すべて広い意味での「アートセラピー」に役立つ作品になっています。
「テトテ」のカテゴリー中の「アート・写真」の中の「イラスト」と、「家具・インテリア雑貨」の中の「ウォールデコレーション」の2ジャンルに登録をさせていただきました。現在は新作なので、すぐに見られます。
何日かすると他の人の新作の画面が先になり見られなくなると思いますが、そのときはニックネームの「コラボレイターズ」で検索していただければ、すぐに見られます。
ぜひご覧をいただき、ご活用したり周りの方にお薦めいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
「dクリエイターズ」については販売クリエイターの手続きに手間がかかりましたが登録はすんでいるので、近々入力します。お待ちください。
トップページに戻る
1月1日(水)
あけまして、おめでとうございます。
皆様方のご多幸、ご健康を心からお祈りいたします。
二年以上前から、心と身体を楽にしていやし心身の健康と人間的な成長などに役立つ、広い意味での「アートセラピー」に貢献できるネットショップをつくりたい思い、作品をつくっていますが、やっと実現のスタート台にたどり着きつつあります。
その間にもインターネットやiPhone、スマートフォンなどのハードだけではなくソフトの発達もいちじるしく、無料のサイトがいろいろとできたので、まずはそれらを活用させていただこうと手続きの準備をしています。あと1週間前後で、載せられればと思っています。
具体的には、クリエイターが無料で作品を展示、販売できる「dクリエイターズ」「テトテ」から始めさせいただきます。どちらが先になるかはわかりませんが。
マンガ家の石田おさむ、イラストレイターの北村卓士さんなどとコラボレイションをしているので、ニックネームを「コラボレイターズ」としました。
石田おさむ氏とは新しい曼荼羅がつくれればと思い、まず両界(胎蔵界と金剛界)の大日如来、釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来などを描いていただきました。北村卓士氏には「七福神と大宝塔」「七福神とダイヤモンド富士」です。
ぜひご覧をいただき、お買いもとめいただければ幸いです。
今年こそ本ホームページの修正、加筆などができればと思っていますが……。
本年もよろしくお願いいたします。
トップページに戻る
2013(平成25)年
1月1日(火)
あけまして、おめでとうございます。
昨年暮れには、衆議院議員の総選挙がありました。投票率が59.3%と低かったわりには、国民の政治家への評価、期待が比較的 率直に現われた結果になったようです。
景気がよくなるような真に新しい日本をつくることに大いに期待したいですが、政治家に期待をしすぎていても無理なので、自分なりに人々、社会へ貢献できることをしたいと思っています。
一昨年から心と身体を楽にして癒し、人間的な成長、健康などに役立つ「ネットショップ」をつくりたい思い、作品(商品)をつくっていますが、意外と時間がかかっています。
今年は開設できるようにしたいと思っています。
インターネットやiPhone、スマートフォンなどの発達は、各ジャンルに大きな影響を及ぼしています。
プラスになる場合にはいいのですが、仕事にマイナスの影響が出て、仕事がうまくいかなくなり、アイデンティティを喪失する人もでてきています。
情報技術の発達に応じて、それらをプラスにできるようにして、新しいアイデンティティを持てるようにすることが大切になっています。
東日本大震災や福島第一原発問題における被災者の身心のケアが遅れているようです。
今年の3月には丸二年になりますが、家族や家を失い絶望する中から新しい希望、生きる意味を見出して生きる人たちがでてきています。
本ホームページ(ナビ1,2)で紹介させていただいたフランクルの『夜と霧』などが、仙台の本屋さんなどで売れて、読まれているようです。
第二次世界大戦のときアウシュビッツのユダヤ人強制収容所などに入れられたフランクルは、絶望の中でも生きる意味を見出して生き抜きました。
3.11で被害にあった人にかぎらず、情報化が進んだため仕事を失いアイデンティティを喪失してしまった人、もういちど考え直したい人など、多くの人々にお薦めします。
本ホームページの解説には不十分なところもありますが、一つの参考にしていただければ幸いです。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
よい年になるようにお祈りいたします。
トップページに戻る
2012(平成24)年
8月31日(金)
8月12日にロンドン・オリンピックが終わった。
女子サッカーの「なでしこジャパン」は残念ながら金メダルをとることはできなかったが、初めて銀メダルをとることができた。すばらしいことである。4年後のリオデジャネイロ・オリンピックでは、また金メダルをめざして、夢をかなえて欲しいものである。
男子サッカーは最初スペインに勝ち、一時はメダル獲得も夢ではないのではと勢いがついたが、残念ながら惜しくも4位で終わってしまった。「なでしこジャパン」がいい刺激を与えているようで、更なる活躍を期待したい。
体操の内村航平が団体戦で失敗したものの個人総合で見事に優勝したことや、女子卓球が団体戦で銀メダルを獲得したこと、女子レスリングの伊調馨と吉田沙保里の3連覇、小原日登美が初出場で金メダルをとったことなどは感動的であった。
女子のバレーボールが韓国に勝ち、銅メダルを獲得したことは意外で、思わぬ喜びを感じることができた。スタッフのデータ分析にもとづいた監督の選手起用が成功したようで、関係者の努力があっての勝利であったようである。
それぞれのメダル獲得者には苦しい地道な努力、立ちはだかる厚い壁の克服など、苦悩を乗り越えてきたドラマもあり、さらなる感動と勇気、夢を与えてくれた。
一方、大きな期待をされながらも、力を発揮できずに敗退してしまった選手も少なくはない。敗戦が大きなトラウマになる場合もあるようである。克服して、ぜひ新しいドラマをつくって、人生のプラスの体験として欲しいものである。
さて現在準備をしている、多くの人々の心と身体を楽にして、健康、人間的な成長などにも役立つネットショップの件であるが、ようやく最初のマンダラの作品の絵ができてきたが、準備は全体的に予定よりかなり遅れている。
最初のアイデアにはなかったが、この7、8月急速に発展したことに蓮(はす)の花の企画がある。
埼玉県行田(ぎょうだ)市の「古代蓮の里」のチラシを6月に見たことがきっかけである。6月下旬に行ったときにはまだ早かったが、7月16日に行ったときには古代蓮に限らず、原始蓮などが満開になっていた。全部で44品種あるようだが、すでに咲き終わっていたものや、まだ咲いていないものもあったので、すべてがみられたというわけではない。
思っていた以上にきれいな原始蓮の写真が2枚撮れた。


泥の中で綺麗な花を咲かせる蓮は仏教では最高の花であり、「胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)」の中心には八葉の蓮が描かれている。
その後、蓮の花による「蓮曼荼羅(はすまんだら)」をつくるというアイデアが浮かんだ。
日本では500品種くらいあるという。一度にすべての蓮を入れた曼荼羅をつくることは無理なので、原型となる基本の簡単な曼荼羅や個別の曼荼羅からつくれればと思っている。
「古代蓮の里」には、7/30と8/20にも行き、4回行って(補:9/3も入れて5回)、合計で41品種が見られた。
蓮は6月下旬から8月中旬くらいが咲く時期のようなので、できる限り今年見て写真を撮っておきたいと思い、次のような所へ見に行った。
上野の不忍池。和蓮の一品種だけであるが、大きな池で蓮が一斉に咲いている景色を見たいと思い、期待して6/28から8/25までの間に7回行ったが(補:9/1も入れて8回)、残念ながらそうしたシーンは見られなかった。
池の場所により咲く時期に差があり、6~7か所くらいに分かれていた。地下水を利用しているようなので、水温の差が開花時期にも影響を及ぼしているように思われた。
個々の蓮の花はきれいであったが、残念ながら全体的に花には勢いがないようにも思われた。去年はよく咲いたとのことである。池が大きいので大変であると思うが、場所によってはもう少し手入れが必要なのではと感じた。もっと華やかに咲けば、人々にもっと感動と安らぎを与えられる名所になると思う。
もし2020年の東京オリンピックが実現した場合には(しなくても)、上野の不忍池に各国の蓮を植えて、国際的な蓮の名所にするといいのではと思えた。
千葉市の東京大学農学部附属緑地植物実験所に350品種があるようなので行こうと思いインターネットで調べたら、残念ながら昨年3月30日に閉鎖となり、西東京市(田無)の東京大学大学院農学生命科学研究科附属 生態調和農学機構に引き継がれて、移植したとのことであった。
今年は7月18日(水)、19日(木)の2日間のみ一般公開されて近くでみられたようだが、それ以外は10メートル離れた縄の外から見られるのみであるという。8/7に行ってみると、蓮が咲いているのはわかるが、やはり近くではみられない。
作業をしていた職員の方と話ができたことは有益であった。蓮の担当の職員は2名で人手が足らず対応できないのだという。なんらかの工夫をして、ぜひ開花中は公開して近くで見られるようにして欲しいものである。
千葉県の香取市にある水郷佐原水生植物園にも350品種あるというので、8/8に行ってみた。
中国の蓮だけで200品種くらいあリ見ごたえがあった。佐原市(現香取市)と南京市とが友好関係にあり、ハナショウブを寄贈したお返しに南京市から蓮を贈られたことから、中国の蓮が多くなったようである。
もちろん、すべての花がみられたというわけではない。早咲きと遅咲きの花があるからである。
府中市、郷土の森公園の修景池へ8/11に行ってきた。大賀蓮など30品種あるが、花が見られたのは12品種で、山場は過ぎていた。大賀蓮で有名な大賀一郎博士の銅像がある。大賀博士は戦後、府中市に住み蓮を育てていた。それらの蓮を集めてつくった池のようで、よく設計された池であった。
調布市の神代植物園にも蓮があることがわかったので、8/15に行ってきた。広い芝生広場のはじに、思ったより小さな甕(かめ)で育てられていた。50品種あり、花が見られたのは4品種で、完全にピークを過ぎてしまっていた。
広い芝生のスペースがあるのだから、もう少し大きな甕で、あるいは池をつくって見せていただきたいと思った。そうすればもう少し長く花が咲くように思わる。
町田市の薬師池公園にも8/22に行ってきた。大賀蓮のみで、8輪くらいが咲いているだけであった。
警備室横の町田フォトサロンの建物に町田市立博物館の「蓮(Lotus
Land)展」(7/7~9/9)のポスターが張ってあり、急きょ行ってきた。
蓮を植物としてみるだけではなく、アジアを中心に欧米の視点も入れて生活、文化、芸術などの作品を収集していて、よい展示であった。
明治30年代に日本を訪れたイギリス人のハーバート・ポンティング(Herbert
G.Ponting)は“In Lotus Land Japan(蓮の国日本にて)”という本を著し、写真と文章で日本の美しい自然や文化を紹介してベストセラーになったという。同書は『桃源郷日本にて』と邦訳されてしまったようである。
19世紀末から20世紀にかけて欧米では東洋を象徴する花、蓮を冠して日本を「Lotus Land (蓮の国)」と呼んだことがあったのを知ったのは有益であった。
現在では蓮は熱帯に限らず温帯の地域、アメリカやヨーロッパ、オーストラリアなど世界中にあるようで、各地へ行き写真を撮っている人もいるようである。
行田市の「古代蓮の里」と上野の不忍池以外はピークを過ぎた後であったので、 来年はそれぞれ見所の時期に行くことと、日本各地の名所(184個所くらいあるようだ)にも行ってみたいと思っている。
今年の夏はロンドン・オリンピックをテレビで見ながら、撮った写真の整理をしたり、見に行く場所の下調べなどをした。
多くの人々に感動して喜んでもらえる美しい「蓮曼荼羅(はすまんだら)」を工夫してつくりたいという新しい夢をもつことができたのは、大きな収穫であった。
早く実現して、多くの人々の心と身体を楽にし健康、人間的な成長などに役立つことができ、日本を真の「蓮の国(Lotus Land )」にすることにも役立つものにしたい。
もちろん、昨年の3.11で亡くなった方々への供養と、残されて生きる人々が元気になり力(エネルギー)が得られる「蓮曼荼羅」ともしたい。
まずは自分で自分に「金メダル」を授賞し受賞できるように、創作に向けて地道に努力をしていきたいと思い始めている。
トップページに戻る
6月5日(火)
早いもので本ホームページをつくって、丸7年が過ぎた。
もっと更新・修正をしたいと思っていたが、できないまま時が過ぎてしまった。
今年になり新しいパソコンやプリンター複合機、ソフト「ホームページビルダー16」などを買ったので、新しいパソコン、ソフトで日記を更新しようと思っていたが、まだ使いこなせず、できないでいる。
古いパソコンで更新しようとしたが、新しいパソコンとプリンター複合機を無線LANでつなぐ作業をしたとき以来、古いパソコンの電源が入らなくなってしまい、使えなくなっていた。
先日、机を掃除して配線を総チェックし始めたところ、電源のプラグがコードの重みでほんの少しズレて接触が悪くなり、電源が入らなくなっていたことがわかり直した。
現在、一人でも多くの人々の心と身を楽にして癒すことに役立つとともに、健康、人間的な成長などにも役立つネットショップをつくろうとして「苦闘」している。
コンセプト、屋号やロゴの案などはほぼ決まり、作品・商品のアイデアもだいぶ多くなった。しかし思った以上に、パソコンやソフト、プリンター複合機などを動かすことに手間がかかったり、作品・商品の制作にも時間がかかっている。
アフィリエイトも有効に活用したいと思っている。よいアイデアや作品・商品などがあれば、ぜひお知らせください。
現在の新しい情報技術の成果などを利用させてもらいながら、遅ればせながら今までの自分の仕事や興味、関心などを発展させながら統合できることに大きな喜びを感じている。
実現して発表できる日が早くくることを楽しみにしながらも、今は生みの苦しみを味わい、悩みながら、忍耐強く、コツコツとこなす日々を過ごしている。
トップページに戻る
1月1日(日)
新年、明けましておめでとうございます。
昨年は東日本大震災や福島第一原発の事故などがあって、厳しい年になりました。
一方、女子サッカー「なでしこジャパン」が世界一になるという明るいできごとがありました。
12月には由紀さおりの1969年に流行った「夜明けのスキャット」がアメリカで大ヒットしているという、もう一つの明るいニュースが入ってきました。
本年は課題の山積する日本が「明るい時代の夜明け」を迎えられるようになればと思います。
「なでしこジャパン」の澤穂希選手は「夢は見るものではなく、かなえるもの」といっていますが、今年のロンドン・オリンピックで金メダルを取って、ぜひ夢をかなえてもらいたいと思います。
ところで、筆者は昨年『マンガ ケインズ』の出版後、次の企画の準備を進める中で、心と身を楽にして癒すことに役立つ「ネットショップ」や「ポータルサイト」をつくってみたいという夢をもつようになりました。
東日本大震災や福島第一原発事故における被災者の身体だけではなく、心のケアが重要な問題になっています。
また自殺者は14年間毎年3万人を超えて、全国の教職員で心を病んで休職している人数は4500人になっているようです。
多くの人々の心身の問題の解決、健康、人間的な成長などに役立つことができればと思っています。
一人でも多くの人々に利用していただけるような「ネットショップ」にしたいと思い、昨年秋から実現に向けて少しずつ行動を始めました。今年中に立ち上げて、「夢をかなえる」ことができればと思っています。
すべての人々にとって、よい年になるようにお祈りいたします。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
トップページに戻る
2011(平成23)年
9月22日(木)
9月11日、東日本大震災から半年が過ぎた。死者1万5781人、行方不明4086人、自宅に戻れない避難者はまだ8万人超にのぼるという。
深刻なのは福島第一原子力発電所の事故により、広島の原爆の20個分以上の放射性物質がもれて汚染したことであろう。
この事故は天災というより、人災といえる。福島第一原子力発電所だけではなく全国の原子力発電所の安全対策を考えると、現在の日本の状況は大変に危機的で深刻である。
将来的には原子力発電所をすべて停止することが理想であろう。しかし原子力発電への依存度を少なくしながら、可能なかぎり、それぞれの原子力発電所を安全に作動させる技術と対応策を研究し開発することは、日本人のために必要なことであるとともに、日本人が人類と科学技術史において貢献することになると思う。
地震、津波、放射能汚染などの被害にあって、不幸な状態を協力し合って前向きに生きようというプラスの面も生じている。
3.11以前には自分だけよければいいという個人主義的な考え方をする人が多かったが、それ以降は自分が人々や社会に貢献できることをしようという人々が増えてきているように思う。
被害にあっても前向きに生きていける人はいいが、深い悲しみや苦しみをかかえている人々の「心の傷」を癒していくことも、今後大切になるであろう。
アメリカでは2001年9月11日の同時多発テロから10年が過ぎたが、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症率は5年以上を過ぎてから増加したという。
9月2日に菅内閣にかわって野田内閣が発足した。大震災からの復興と新生を含めて、日本経済を立て直すとともに、きめ細やかな心のケア対策が望まれる。
9月11日に女子サッカーの日本代表「なでしこジャパン」がロンドン五輪アジア最終予選最終日で中国を1:0で下し、通算4勝1分の1位でオリンピック出場を決めた。
来年のロンドン オリンピックで金メダルを取りたいという夢にむかって一歩前進をしたことは、すばらしいことで、ぜひ夢を叶えてほしいものである。
佐々木則夫監督と彼女たちの言動とプレーは、日本人に元気と勇気、感動などを与え続けてくれるであろう。
9月14日に「空海と密教美術展」(東京国立博物館、9月25日まで)へ行ってきた。最近は若い女性のあいだでも仏像鑑賞がブームになっているという。平日の正午前であったが、すでに入口で30~40分の入場規制をするほどの人気であった。
今回の美術展では3mくらいの大きな「両界曼荼羅(マンダラ)」(密教の宇宙観・世界観を表した図で、すべての仏などが描かれている)が見られるものと思って行ったのだが、二つ一緒の展示ではなく、胎蔵界と金剛界のマンダラを一つずつ交互に展示しているということで見られずに残念であった(少し小さいマンダラはペアで展示されていた)。
金剛界と胎蔵界の二つの「両界マンダラ」を見ていると、心が広くなリ安らぎが得られて癒される。特に大きなマンダラには独特の迫力とパワーがあり、心理学的な効果があるように思う。
禅宗では丸い円の円相を描くが、これはマンダラを一筆で描き表したものといえるであろう。
深層心理学者ユングはフロイトと対立し、別れてから心の病になるが、抽象的な「胎蔵界マンダラ」の絵を描いたときに、心の病が治る体験をした。
筆者は7年前に京都の東寺へ行ったとき「両界マンダラ」のポスターを購入し、カメラの量販店で金色のわくのパネル(アルミ製、一つ2000円強、トタールで1万円弱)を買って入れて部屋に飾ったところ、部屋だけではなく自分の暗い心が明るくなり心を癒してくれるようになった。
高いお金をかけなくても、マンダラは心に安らぎを与えてくれるので、ぜひお薦めしたい。
今回もう一つ期待していたのは「仏像マンダラ」であった。
京都の東寺の「立体マンダラ」21体のうち、8体で構成されていた。5菩薩のうち2体(金剛業菩薩、金剛法菩薩)、5明王から2体(大威徳明王、降三世明王)、6尊のうち4体(梵天、持国天、帝釈天、増長天)、計8体である。中央の5仏からは1体もなく、特に中心となる大日如来がなかったのは残念であった。
東寺の講堂の「立体マンダラ」の仏像21体は正面の側から拝観する形であるが、今回の展示では仏像間を自由に歩いて鑑賞できるようになっていた。これは大変よい試みであった。しかし、時間がたりなくなってしまったことと、観客数が多すぎて(喜ばしいことではあるが)静かに鑑賞できなかったことは残念であった。
なお、先ほどの深層心理学者ユングは晩年に仏像ではないが塔の「立体マンダラ」をつくり、心の安らぎを得てから亡くなっている。
ところで、女子サッカー「なでしこジャパン」は選手、監督、スタッフなどが個々の能力を生かして調和の取れた強い「人間マンダラ」のチームをつくり上げて、よい結果をだしているといえる。
選手20人と監督1人をたすと21人になる。東寺の「立体マンダラ」は21体である。21人(体)で一致しているのは偶然であるのかもしれないが、21という数字には、どんな意味があるのであろうか?
ご存知の方がいれば、ぜひお教えいただきたい。
今後、日本は3.11の不幸な体験を生かしていくために、すべての人々の生命と個性、能力を生かせるような「人間マンダラ」の社会、日本にしていく必要がある。
そのためには政治家の活躍に期待しすぎるのではなく(国民の税金負担を減らすために、まず政治家の人数を減らすことが望まれる)、経済学者、科学技術者、医師、精神科医、心理学者、宗教者などにかぎらず、すべての人々の持てる能力と個性を生かして、「人間マンダラ」の社会と世界にすることに貢献しあうことが必要になっている。
筆者も自分にできることを、ささやかでもさせていただこうと思っている。
「両界マンダラ」や「立体マンダラ」などからなる「密教美術」は人々の心を癒やし命を救う最高の「アートセラピー」であるとともに、日本や世界のあるべき「人間マンダラ」の社会への指針をも与えてくれているように思われた。
京都の東寺や高野山などへまた行ってみたいと思わせてくれる「空海と密教美術展」であった。
トップページに戻る
7月26日(火)
女子サッカーの第6回ワールドカップ、ドイツ大会で日本代表「なでしこジャパン」が今月18日の決勝でアメリカを2:2の後、PK戦で下し優勝して「世界一」となった。
彼女たちの決してあきらめないプレーは、東日本大震災にあった人々だけではなく、福島の原発問題をふくめて、政治・経済・社会など、さまざまな分野で大きな問題をかかえて暗くなっている日本人に大きな感動と元気、勇気などを与えてくれた。
来年のロンドンにおけるオリンピックで金メダルを取りたいという夢を、堂々と語る彼女たちに頼もしさを感じた。
ぜひ実現して欲しいものである。応援したい。
さて一昨日24日(日)にテレビのアナログ放送が東北3県以外で終わり、デジタル放送の時代になったが、最近、もう一つ大きな時代の変化を象徴する出来事があった。
それは、5月20日の新聞などで小さく報道されていたのだが、アメリカのインターネット小売(通販)大手のアマゾンで電子書籍が紙の本の販売を上回ったことである。
アメリカでは、予想を上回る早いスピードで、本のデジタル化も進んでいるようである。
一方、日本では電子書籍の端末が売り出されるとともに、大手出版社を中心に電子書籍が販売されているが、これからという状況であろう。
スマートフォン(高機能携帯電話)の普及は、日本における電子書籍化をいっそう進めることになりそうである。
小生のところにも、ある出版社から既刊のマンガ文庫本2巻の電子書籍化の申し込みがあった。
携帯電話のサイト「まんが王国」で配信されているが、サイト全体の配信点数が多く、埋もれてしまい地味な反応であるというのが正直なところである。
多くの人々に見られるようにするためには、それなりの工夫が必要であるように思われる。
これから、しばらくは新刊書も電子書籍を同時に出版する時代になるようである。 もちろん、紙の本の新刊書より早く電子書籍を配信してから、後で紙の本を出版するということも考えられる。
2巻に限らず、電子書籍に前向きに取り組んでいきたいと思い、少しずつ準備を始めつつある。
技術革新の大きな変化は「‘昔’通りの仕事(の仕方)」を通用させなくなり、多くの人々にプラス、マイナスの両面で大きな影響を及ぼす。
時代の大きな変化に対応をして、いい作品、本、商品などを創り出すためには、決してあきらめないで戦い続けるという「なでしこジャパン スピリット」が必要であろう。
「世界一」をめざす「なでしこジャパン」の活躍は、サッカーなどのスポーツ界だけではなく、各界に精神的(心理的)にも大きなプラスの効果を及ぼすものと思われる。
優れた点を学ばせていただこう!
トップページに戻る
5月5日(木)
ご無沙汰しました。
1年5か月ぶりの「日記」となります。
本HPを立ち上げてしばらくしたころに、ある先輩から細山君の「日記」は「日記」ではなく「月記」だといわれたことがありましたが、「月記」ではなく「年記」になってしまいました。
さて、3月11日には日本の観測史上最大のマグニチュード9という大地震が東日本に起こり、死者14,785人、不明者10,271人という大惨事になってしまいました(5月4日現在)。
被害にあった方々には心からお見舞い申し上げます。
また亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします。
日本は百年に一度といわれる大不況を解決しつつあったときに、大地震に見舞われてしまい、しかも津波の影響で福島の原子力発電所が故障して、放射能が漏れ始めるという大変な事態になっています。
日本社会に与える影響は大きく、世界的に見た場合に日本の国際的な信用は揺らぎ、想定外の「日本の歴史始まって以来の存亡の危機を迎えている」といっても過言ではないのかもしれません。
ところで、『マンガ ケインズ 大不況は解決できる!』(小島寛之=監修・解説、石田おさむ=画、細山敏之=作、講談社、本体価格1500円+税)が、4月26日(火)に発売されました。
1年半くらいでできればと思っていましたが、2年4か月かかってしまいました。
ケインズ(1883~1946)は、不況で大量の失業者がでていた当時のイギリスと世界の経済問題を解決しようとして生きた経済学者です。
2008年9月のサブプライムローン問題以降の「百年に一度の大恐慌」において、「今の時代に頼りにすべき経済学者は一人しかいない。それはケインズだ」と再び高く評価され始めました。
本書では、なぜケインズが再評価されることになったのかを明らかにしました。
ケインズのマクロ経済学は、「弱者の命を救う経済学」「お金の再分配をする経済学」であるといえるように思います。
東日本大震災や福島の原発問題を含めて日本が復興し、新生をするためには、税金や国債、福祉、年金、公共投資、雇用の創出、科学技術の開発などの「新しい日本社会におけるお金の流れのシステム」をつくる必要があり、ケインズ経済学を応用して解決していきたいものです。
ケインズは国家公務員、大学の講師と職員、経済ジャーナリスト、経営者、投資家など多ジャンルで活躍しましたが、倫理哲学をもち心が広くスケールの大きな人間で、まだ日本にはいないタイプです。
社会貢献を積極的にしていくケインズの生き方、精神(「ケインズ スピリット」)は、われわれにエネルギーと勇気、知恵などを与えてくれます。
ぜひ本書が多くの人々に読まれて、日本を再生、新生して「身も心も楽楽」となる社会にすることに貢献できることを願っています。
また若い人の中からケインズのような経済学者が出現することにも役立てればと思っています。
ご協力、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
トップページに戻る
2010(平成22)年
1月1日(金)
新年、明けましておめでとうございます。
今年も厳しい年になるのかもしれませんが、明るくいい年にしたいですね。
厳しい時代であるからこそ、お互いに自分のことばかりを考えて生きるのではなく、人々、社会のために自分は何ができるのか、何をさせていただくことができるのかを考えて、できることに自分の命を使い、心の発達・進化をして生きることが大切になっていると思います。
今年は昨年から手がけていた経済ものの企画を仕上げて実現させたいと思っています。
現在のデフレ日本のかかえる諸問題を解決するためには、優れた政治家が出てくる必要がありますが、それ以上に優れた経済学者の出現が望まれるように思います。
日本にも優れた経済学者が多くなっているようですが、現在と将来の日本がかかえる問題(内需と外需のバランス、失業と雇用の問題、ワーキング・プア、848兆円の赤字国債、高齢化・少子化社会など)を解決するための政策をつくるとともに、それを理論化できるスケールの大きな経済学者です。
両方ができれば、日本人として初めて経済学のノーベル賞を受賞できるのではないかと思います。
東洋の日本の問題を扱っても西洋の問題と異なるので普遍化はできないという経済学者の意見を新聞で読んだことがありますが、そうではないのではないかと思いました。
日本という特殊な国の問題ではありますが、理論化して解決をするということは普遍化することですので、他のアジアやアフリカの国々、場合によっては先進諸国などにも役に立つ可能性がでてくることになると思います。
現在手がけている人物は日本にはまだいないスケールの大きなタイプで、日本の若い人におおいに参考になりますので、少しでもお役に立てればと思いながら取り組んでいます。
またジャンルは異なりますが、仏教ものの企画も進めて、その後、以前から考えている心理ものを、そろそろ実現できればとも思っています。
いずれも、もう少し進んでから公表します。
本ホームページのタイトルは「こころ楽楽」ですが、心だけではなく、自他ともに心も身も楽になることに役立つものにできればと思っています。
つまり、「心身楽楽(しんしんらくらく)」です。
本HPを大幅にバージョン・アップし修正もして、更新回数を増やすことも、わが夢と希望の一つですが、まだできないかもしれません。
早くできるようになればとは思っていますが……。
いずれにしても、よい年になるようにお祈りします。
本年も、よろしくお願いいたします。
トップページに戻る
2009(平成21)年
12月26日(土)
先日、ある高校三年生から体験談「私の精神科歴」のメールをいただきましたので、ナビ5『「心の5段階説」と「心の10段階説」』に細山の感想文などとともに掲載をしました。
デフレの時代に入り、経済的にも精神的にも苦しむ人々が多くなっています。
少しでもお役に立てればと思っています。
今年も残すところ、あとわずかになりました。
個人的なことでは、科学のマンガ本の文庫化は既刊本の売れ行きが鈍いということで、残念ながら中断してしまいました。
携帯電話によるマンガ配信は伸び悩みという状況です。
明るい前向きな話題としては、ある経済学者などのマンガ本をつくる企画が決まったので、シナリオを書いています。
しかし、初版部数が少なく定価も高めなので経済的には厳しい仕事で、多くの読者に読んでいただけるようにするために、大いなる工夫が必要になっています。
本当は定価が安くて初版部数が多い本にできたらいいのですが、出版社でも初版で採算を取り返品を少なくして在庫をかかえないようにしたいというのが現状のようです。
理想的な形で出版できないのは、自分の力がまだたりないということでもありますが……。
経済学のジャンルは今までに手がけたことがなく、土地勘がないので思ったより時間がかかっています。
それと日銭を稼ぐ仕事もする必要があり、時間があまり取れず予定通りには進まず、かなり遅れてしまい関係者に迷惑をかけてしまっています。申し訳ありません。
まだ苦しんでいますが、ほぼ山場を越えつつあります…。
できるだけ資料を読んだり、シナリオを書くことに時間を使うために、本ホームページの更新に時間を使うことはできませんでした。
今後も時間的に余裕ができるまでは、あまり更新できないと思いますが、ご了解ください。
なお、不況と失業の解決をめざして財政投資をする彼の経済学は、原則的には現在世界的に実行されていて、大きな力を発揮しているといえます。
広い意味では日本でも少し変形のバージョンといえますが、実行されているといえます。
彼の経済学がなかったら、世界はもっと大混乱におちいり悲惨な状況になっていたと思います。
世界的な大不況であったとしても影響を最小限にとどめて、かなり多くの人々が通常通りの日常生活を営めるのは、彼の理論があったからだともいえます。
経済学の大切さと、彼の理論が多くの人々を救っている「凄さ」を感じます。
現在、デフレの日本では倒産や失業、ワーキング・プア、高齢化,少子化、財政など多くの問題をかかえていますが、彼の経済学だけではなく、時代とともに多彩な能力を発揮して生きた彼の生き方は、特にこれからの若い日本人に大いなるヒントを与えてくれます。
デフレ社会における経済的、精神的な苦しみは人ごとではなく、自らの問題でもありますので、マンガ本の出版がデフレ社会の問題を解決していくことに少しでも貢献できればと思っています。
また、現在とこれからの日本の経済問題を解決するためには、新しい政策と新しい経済学の理論がつくられる必要があると思いますので、広い意味でそうしたことにも役立てればと思います。
本年もお世話になり、ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
トップページに戻る
3月30日(月)
桜の花が咲き始めたものの冬並みの寒さで二分咲きくらいのようですが、今週は満開になるのかもしれません。
先日、講談社の松岡さんから、『マンガ 「日本」書の歴史』魚住和晃・編著、角田恵理子・執筆、櫻あおい/栗田みよこ・画(3月6日発売、四六判、上製、368頁、本体価格1900円)をいただいた。
日本への漢字の伝来から唐書法の浸透、仮名文字の誕生と発展を含めて、近代までの書の隆盛が描かれ解説されていて、日本の書の歴史がわかりやすく面白く理解できます。
同書は『マンガ 書の歴史[殷~唐]」』魚住和晃・編著、櫻あおい・画(2004年5月発売、四六判、上製、256頁、本体価格1600円)、『マンガ 書の歴史[宋~民国]」』魚住和晃・編著、栗田みよこ・画(2005年11月発売、上製、四六判、304頁、本体価格1800円)に続く本である。
あわせて3巻を読むと、日本と中国の書の歴史の全貌が理解できるようになっている。
マンガ本としては定価が高めなので売れ行きが気になったが、いずれも好評のようで重版されているという。
不特定多数の人向けというより、ぜひ読みたいという読者に確実に買われているようだ。
書名に「マンガ」とうたっているが、完全にマンガですべてを描いているというわけではなく、解説のページとマンガのページをうまく組み合わせて、切り口に独自の工夫をしている。
細山の考えていたマンガ本というイメージより広い視点から編集されている。
ところで、松岡さんとは25年位前に知り合ったのであるが、昨年5月に文庫の原稿(『マンガ ニュートン』)を講談社へ届けに行ったとき、たまたま談話室で声をかけられて、打合せが終わってからしばらくぶりに話をした。
話の途中で、ある人物のマンガ本をつくってみたらといわれたのだが、手がけるジャンルがまた広がってしまうので、このときは正直なところ、あまり乗り気ではなかった(ここにまだ名前を書けないのが残念ですが、『マンガ ニュートン 万有引力入門』(講談社+α文庫)をお読みいただくとすぐにわかります)。
ところが、昨年後半から世界的な大不況になり、今年1月4日の新聞を見ていたら、この世界的な大不況を解決する考え方で頼れる人物は彼しかいないという記事がでていた。
1月下旬に別の文庫本の原稿を届けに講談社へ行ったとき松岡さんとまた話をしたら、まだ関心を持たれていたので、すぐに資料を読み始めて企画書をつくってみた。
正式な決定はまだであるが、生き方を含めて人間的にも非常に面白い人物で、この大不況を解決するために彼の考え方にもとづいた政策が各国で実行され始めているので、ぜひ実現できればと思っている。
ただし、不況の影響が出版界にも及んでいて全体的に本の売れ行きが鈍くなっているようで、初版部数が少なく定価が高くなる可能性がある。
衣料関係のジャンルで好調な「ユニクロ」的な安い本にして多くの人に読んでもらえればと思っていたが、上記のような定価の高めの「ブランド」的な本つくりをしないといけないようである。
悩み苦しんでいる人(自分を含めて)を救うだけではなく、悩み苦しむ人が少なくなり人生を楽しめる社会、国をつくることに大いに役立つ本にできるよう、さらに独自の工夫をしていきたいと思っている。
トップページに戻る
1月1日(木)
新年、明けましておめでとうございます。
昨年のアメリカのサブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響で、日本の産業、社会は大きな打撃を受けて、今年は厳しい年になるようです。
職を失ったり倒産をして絶望してしまう人が多くなリ、残念ながら自殺者が増えてしまうものと思われます。
しかし、この危機、逆風はチャンスだという見方もあります。
チャンスとするためには萎縮することなく、前向きな課題を設定して挑戦し、前進をすることが成功につながるといわれています。
人間は自分のことばかりを考えて「自己中心」的に生きていると、どこかで不安になり行き詰ります。
絶望を感じたときには自分のことを考えることをやめて、他者、社会のために自分は何ができるのか、何をさせていただくことができるのかを考えて、できることに自分の命を使って「他己中心」的に生きていくことが、「心の病」にならないコツのようです。
また、こうした時代であるからこそ、自分のことだけを考えて生きるのではなく、自分なりに「他者のために、社会のために何をさせていただくことができるのか」を考えて生きていくこと(「心の進化」)が必要で、それができると心の中に喜びを感じて、道が開けてくるように思います。
自分(自我、己)を捨てて、自分の命を有意義に使って生きていきましょう!
昨年11月に『マンガ ダーウィン 進化論入門』(講談社+α文庫)が出版されましたが、今年はダーウィン生誕200年で、『種の起源』出版150年に当たります(本HP、「ナビ11」参照)。
ダーウィンの進化論は自然の中における種の進化を論じたものですが、彼の生物(生命)に対する観察力や探究心、根気、勇気などには感銘を受けます。
現代の人間は自然とともに社会の中で生きています。
つまり、自然と社会の二つの環境の中で生きているといえます。
昨年から「社会環境」が激変し始めているわけで、その「社会環境」に適応をしながら、人々のお役に立つという「変異」、つまり「心の進化」をすれば、不安、絶望を乗り越えて生きることができます。
また今年は、ガリレオが1609年に人類史上初めて自作の望遠鏡で天体を観測してから400年になり、「世界天文年」であるとのことです。
昨年8月には『マンガ ニュートン 万有引力入門』(講談社+α文庫)が出版されましたが(本HP、「ナビ11」参照)、ニュートンの「万有引力の法則」を含む成果は、地球上だけではなく宇宙について考えるときにも不可欠で、 「世界天文年」に読んでいただくにふさわしいマンガ本であると思います。
彼が発見した「万有引力の法則」は宇宙望遠鏡を打ち上げるロケットや人工衛星を軌道に乗せるための大きな基本の法則となっていて、彼の法則がなければ不可能といえます。
ニュートンは反射望遠鏡も作り、天文学の発展にも大きく貢献しています。
厳しい「社会環境」にあるからこそ、「人間社会」や自分のことだけにとらわれずに、科学者と科学の歩みを知ることは人間の「心の世界」を広げて心を癒し、宇宙や生物などの大自然の中の人間について、また自分について考え直すことに役立つと思います。
既刊の2巻のマンガ本は「心の開放」をすることにも役立つと思いますので、ぜひお読みいただければ幸いです。
今年は既刊の2巻が重版されるとともに、『マンガ ワトソン&クリック DNA入門』『マンガ ガリレオ 天文学入門』(仮題)などが出版できるようにして、心の発達に役立つ「科学楽」(科学を楽しむ学問ならぬ「楽問」)の発展にも貢献できればと思っています。
ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
いずれにしても、お互いに「心の進化」をして、よい年にしましょう!!
トップページに戻る
2008(平成20)年
7月30日(水)
Dellのパソコンを買いWindows XPのソフトを使って、3年半くらいになる。
最初はNTTのADSLで使っていたが、一昨年マンションにBフレッツの光回線が引かれたので変更をした。そのため利用料金が少し安くなった。
しかし相変わらず勉強不足で、ソフトを十分に使いこなせていないでいる。
この7月に、パニックになりそうになったことがある。
ウィルスに本格的に汚染されそうになったのである。パソコンの画面を立ち上げると最初に一面の青い警告文が出て、対策が必要だというのである。
しかも全文が英語なので意味がわかりにくく、調べてみると183個のウィルスが入っているというのだ。
McAfeeのウィルス対策のソフトを入れてあるし、ワープロソフトやメール、インターネットもいつも通り使えたので最初は無視をしていた。
ところが、McAfeeのソフト更新のお知らせが時々画面に出るので操作をして、「修正」ボタンを何度クリックしても、なかなか更新されないし(これは半年以上前から今でも続いている)、別の英文の警告文もひんぱんに出て消えないようになったので、操作をしていくと、英文で‘Antivirus
XP 2008’‘AlphaWipe Tracks Cleaner 2008’などの別ソフトを買ってダウンロードをして操作することが必要だという。
McAfeeの画面には問い合わせのメールが直接できるようにはなっていなくて、電話をするのも面倒なので(書類を捜したり、電話をしても機械操作になっていてパスワードなども必要で人間と話すことができるまでに待たされて時間がかかると思い)、英文の画面を辞書で調べながら読んでいくと、最初はソフト代が3385円か4515円になっていたが、申し込みの操作をしていくと、結果として11,783円の買い物になってしまった。
英文のソフトをダウンロードして、意味もあまりよくわからないままに夢中で操作をしていくと、ウィルスを全部駆除できたようで、警告文も出なくなったのでホッとした。
ただし、ワープロソフトを使っていると、急にパソコンの電源が切れることが2,3回あったので、気にはなっている。再起動をすると、更新した文章は保存されているので、直接の被害はないのだが…。
このソフトはアメリカのStaff www.paymentbit.netというところから送信されてきたが、ここはMcAfeeの会社ではなく、McAfeeお薦めのソフト会社のものということになるのであろうか?
いま入れているMcAfeeのソフトが役に立たず、肝心なときには別のソフトが別料金を支払って必要になるというのでは、お話にならない!
パソコンがDellというアメリカのメーカーのものであるからなのか、あるいはウィルス対策ソフトがMcAfeeであるから英文の警告文が出たり、英文のソフトが必要になってしまうのかはわからない。
あるいは、これはウィルスとセットで仕組まれた「ワナ?」ということになるのだろうか?
どなたか、ご存知の方がいたら、お教えください。
ウィルスが入った原因は、一日平均5個~10個くらいの英文などの迷惑メールが入るのだが、その中に最近たびたび映像を見るメールが入っているので、これをみようとして開けたことが原因だったのかもしれない。
個人のメールアドレス宛てには迷惑メールはほとんど入らないのだが、ホームページ用のdream.comのついたアドレスに英文の迷惑メールが入る。
その中には、自分の2つのアドレスとは関係のない他人のアドレス宛ての英文迷惑メールがある。
なぜ自分のアドレスとは関係のない他人のアドレスのものが入るのか、最近気になっている。
プロバイダーはocnなのだが、面倒なのでまだ連絡をしていない。
いずれにしても、他人のパソコンにウィルスを送るという反社会的な行為はやめて欲しいものである。
IT技術はだいぶ進歩したが、「人間の心」はまだ進化、発達していないようである。
インターネットやメールなどを願望や欲望を満たすことに使うのはよいとしても、悪用して犯罪をすることは避けたいものである。現在はまだ人間の「心の発達」に利用されることが少ないようで、今後の課題であろう。
6月6日(金)
竹間忠夫著『「家庭菜園」 この素晴らしい世界』(本体価格1500円)が本年2月25日に講談社から出版された。
刊行後、著者から2回ほど電話があった。しかしタイミングが合わず会えなかったので、まだ本をいただけていなかった。
ところが4月末に文庫の件で講談社へ行ったとき、同書の編集をされた松岡さんと偶然にお会いしたので事情を話したところ、本をいただけた。
竹間くんは「週刊現代」の記者などをへて、現在は経済ジャーナリストとして活躍している。
毎週土曜日の週イチで20年間、家庭菜園を続けてきたようで、その経験をふまえて、家庭菜園の楽しみ方と苦労、問題点などが「本音」で綴られていて楽しい本となっている。
野菜づくりの本は多いことから避けて、本書は家庭菜園の楽しみ方などに重点がおかれている。
たとえば、土地を持っている地元の農家の人からの土地の借り方やお礼の仕方など、本書ならではのことが書かれている。
無農薬・有機農法でしているので、虫取りや草取りに手間取るようである。
野菜をつくる喜びだけではなく、家庭菜園を通じて地域の人と出会える喜びもあるとのことである。
これから家庭菜園をしたいという人などには、ぜひお薦めしたい本である。
心理療法として園芸セラピーや森林浴などが注目をされているが、植物と接したり育てることは心が癒されるだけではなく、自然の季節の変化や生命の不思議さ、人間だけが地球に生きているのではないことなどについても実感し学ばせてくれて有益である。
植物についての細山の個人的な思い出としては、父親がなくなったときにサツキの木が150~200本(鉢)くらいあり、引き継いで枝づくりや水をやったことがある。しかし時間がかかりすぎて大変で、2年目くらいで地植えにしてしまった。
母親や兄も植物が好きで、母親が隣の土地が空いていたときに家庭菜園をしていたことがある。
今は高齢になり足が弱まってきたので、自宅の庭の手入れが十分にできなくなってきたので、草取りなどを手伝う必要がでてきた。
切られてもすぐに芽をだす笹やシダ類、コンクリートのわずかな割れ目からも芽を出し成長をしていく雑草の生命力の強さなどには学ばさせていただかないといけないと思いながら、休みの日に手伝っている。
話は変わるが、先月中旬に㈱大手広告通信社の千崎研司さんからウェブサイト「ブランディング出版.com」(本HP、ナビ10「リンク、リンク、リング」参照)をオープンしたというメールをいただいた。
千崎さんは新聞社の出版部に勤めていたこともあり、本日記ページ(2006年5月26日など)で紹介をさせていただいたように明治書院から出版された本などについてプロデュースをしている。
それらの経験をもとに出版事業を発展させて、今回のウェッブサイトを開設したようである。
「ブランディング出版」は本の著者が費用を負担する自費出版形式ではあるが、著者の企業のブランド力を高めるためにブランドのある出版社から刊行することを意味しているようである。
同社は広告代理店であるので、本を出版することだけではなく、もちろんプロモーション展開を総合的にプロデュースしてくれる。
今後さらに「いい本づくり」をしてヒット作を生み出して、出版事業(「ブランディング出版.com」)自体のブランド力も高めていってほしいと思う。
一つの新しい面白い試みであリ、成功を祈りたい。
4月14日(月)
最近はインターンネットを利用した学習サイト、講座が盛んになってきているようだ。
内容は語学学習からパソコンのソフト、仕事のスキルアップ、生活、趣味、雑学検定まである。
これらは受講料が有料のものと無料のものに分けられ、無料のものは広告収入をもとに運営されている。
先月、ネット講座を運営しているナレッジサーブという会社から、ホームページを見たのだが講師としてメンタルヘルス関連の魅力ある講座を開設しないかというメールをいただいた。
同社のネット講座は、カルチャー系とプロフェッショナル系に分かれていて有料である。
前者はライフスタイル、美容・健康、趣味、マネー・法律、語学・受験という5分野、後者は資格取得としてIT関連、国家資格、キャリアの3分野とインターネット・パソコン、ビジネススキルを合わせて5分野になっている。
受講料は講師がきめて、総額のうちの80%を講師が受け取り(月額基本料9000円が引かれる)、20%を同社が得るというシステムである。
詳しくは、本HPのナビ10「リンク、リンク、リング」で同社のHPをリンクさせていただいたので、ご覧ください。
本ホームページは細山にとって一つの「実験の場」でもある。
専門家の視点、立場とは異なる「一人の人間」としての独自の視点から深層心理学を楽しみながら、「心の底から楽しく生きられる」ことに役立つことを目指している。
つまり、深層心理学を専門家だけのものにしておくのではなく、多くの人々に役立つ「市民のための深層心理学」、つまり「深層心理楽」として、その普及に役立つものにしたいと思っている。
本HPの一部を発展させれば、別に「深層心理楽」の講座がつくれると思う。
将来的には有料のものとは別に、10代~20代の若い人のために無料の講座もつくれればと思う。
つい最近も、「誰でもいいから人を殺したかった」という殺人事件が起きている。
こうした攻撃的な死の本能(タナトス)と性を含む生の本能(エロス)のバランスが崩れて心の歯車が狂い、タナトスがむき出しになり、人を殺す人間が今後も出てくる可能性は絶えずある。このことは本HPで何度も書いている。
できれば、殺人をしてしまった10代から20代の人を含めて、心を発達させて更正や防止に役立つ内容の講座(自殺も含めて)もつくれればと大胆に思っている。
有料の講座は、20代以上の人が心の病にならないための「心の発達」に役立つ内容ということになる。
特に今まで活躍してきた人が30代の後半から40代、50代になると、立場や技術革新、社会、時代の変化に適応できずに役割が終わってしまい、若いときのアイデンティティが通用しなくなり苦しんで心の病になっている場合も多い。
「第二(あるいは第三)のモラトリアム現象」が生じているように思われる。新しい「第二(あるいは第三)のアイデンティティ」を発見して「心の発達」ができれば、心の病は治る。これは日本人の寿命がのびた中で、定年後の「アイデンティティ」の発見に役立つ講座にもなる。
いずれにしても心の病にかかる人が多くなり、社会的な犯罪を少なくするためにも、「心の問題」を専門家だけにお任せするのではなく、自らが自らの心を発達させて社会に貢献しながら人間として成長をしていく人が多くなることが、「いい人生」、「いい社会」にするためには必要不可欠になっている。
話は一度変わるが今年の1月に、ベストセラーを多く出版している中堅の出版社に勤めていた編集者の方が本HPを見てくれて話をしたところ、単行本の原稿としてまとめたらといわれた。できるだけ細山の言葉でやさしく書いたほうがよいとのアドバイスもしてくれて、原稿ができたらみせてくれればといわれた。
本ホームページをつくってから丸3年になろうとしている。
目先のことにおわれてしまい時間が取れずに、あまり更新ができないでいる。
しかし人数は多くはないが、細山のねらいや内容を適確に理解してくれる人が現われてくれることは嬉しいことである。
昨年から手がけてきた携帯電話によるマンガ配信の件は、だいぶ遅れていたが、もう少しで8巻が配信される。
また、文庫化の件もスタートし始めることができた。
合間を見ながら、先の編集者のアドバイスを意識して、できるだけ多くの人々に真に役立つ単行本を、まず2冊くらいは書きたい。そのことがネット講座を開設するために必要なのではと思い始めている。
それぞれのことを有効に連動させるためにも、本HPが大切になっている。新しい頁を付け加えることも考えている。
いずれにしても自分なりに、人々、社会におおいに貢献できるようにしたい。
1月1日(火)
あけまして、おめでとうございます。
皆様方のご健康とご多幸を心からお祈りいたします。
本年も、よろしくお願いいたします。
最近、気になっている言葉に、「和をもって貴(とうと)しとなす」という聖徳太子の十七条憲法の言葉があります。
聖徳太子は仏教を日本へ導入しましたが、この言葉、考え方は政治の残酷な状況、地獄を見て苦しんだ中から生まれてきたのだと思う。
この「和をもって貴しとなす」という言葉、考え方は、国家、社会、会社や組織などの人間関係における人と人との和だけではなく、次の二つの視点から現代的に意義があり不可欠になっている。
一つは国際的な視点からで、民族間や国家間にも広げられる必要がある。
これは、昨年の暮れに起きたパキスタンにおけるブット元首相の暗殺、イラク、アフガニスタン、パレスチナ問題などを見れば、一目瞭然であろう。
イスラム教やキリスト教、ユダヤ教などの国においても、聖徳太子のような考え方のできる指導者が出現する必要がある。
もう一つは、人間の心の問題、生き方においてで、大変に意味があり深みのある言葉であると思う。
フロイトによれば、人間は攻撃的なタナトス(死の本能)とエロス(性を含む生の本能)に突き動かされて、自己中心主義的に生きやすい。
自分の心の中にタナトスとエロスの和(調和)をつくれれば、心は安らぎ心の病にはならない。
また、殺人や自殺、自爆などもすることはない。
そして、身近な男女の和がつくれれば、男女ともに心の病にはならず、もちろん殺人や自殺、自爆などもすることはないであろう。
男女の和がある環境の中で、愛や慈悲の大切さを知った子どもたちが育てば、和(平和)のある国家、国際社会、世界がつくられていく。
「和」の状態をつくり出すには努力、工夫、能力などがいる。
今年は個人的には目先の仕事をこなしながら、限られた時間の中で、ここ5,6年考えてきたことを工夫してコツコツと実行、実現していこうと思っている。
つまり、まず自分の心の中に和をつくり、人と人、男と女、社会の中に和をつくり出すことに役立てればということである。
それは深層心理学や宗教、科学などからみても説得力のある「和の理論(哲学?)」をつくり、「和術」を実践していくことにもなる…。
トップページに戻る
2007年(平成19年)
12月7日(金)
先日、学生時代からの友だちである作田稔君から『時代を拓く キャリア開発とキャリア・カウンセリング』(日本キャリア・カウンセリング研究会、本年11月刊行、本体価格2667円+税)が送られてきた。
同書は、組織心理学の開拓者であるエドガー H.シャイン博士(アメリカのMITの名誉教授、邦訳書に『組織心理学』岩波書店など)が昨年11月に東京と大阪で行なった講演とシンポジウムをまとめた本である(講演は対訳になっている)。
キャリア開発やキャリア・カウンセリングなどの専門家である金井嘉宏、渡辺三枝子、横井哲夫、木村周、今野能志、小澤康司氏がパネリストなどになっている。
自分の関心・能力を会社・組織の中でどう生かしたらよいのか、また会社・組織は社員・スタッフの関心・能力をどう生かしながら成長し発展していくのがよいのかを考える上で有益な書である。
日本キャリア・カウンセリング研究会(JCC)は特定非営利活動法人で、設立されて10周年がすぎたが、本書はその記念企画である。
シャインプロジェクト実行委員会の一人として作田君が出版企画を担当している。
同書にご関心のある方、あるいは購入を希望される方は、同協会のホームページ(http://www.npo-jcc.org/)をご覧ください。
なお、ジャンルは少し異なるが、細山の関心のある深層心理学者ではアドラーやエリクソンが仕事と人生などについて考える上で参考になる。
特に、会社・組織に入る前の若いときや会社・組織をやめたり離れたとき(途中退社、定年など)に有益である。
さて、早いもので12月になり、今年も残すところわずかとなりつつある。
現在、携帯電話によるマンガの配信と文庫化の準備、他の仕事などの件で、本HPの更新の時間がとれないでいる。
頭の中では簡単にできるものと思っていても、イザしてみると意外と時間がかかってしまうということが多い。
早くHPの各頁を更新したり、バージョンアップできる時間が取れるようになればと思っている。
そのためには新たな工夫と行動が必要なようで、少しずつ準備をして来年には動いてみたいと思っている…。
9月27日(木)
先月下旬に、3年3か月間くらい使ってきた携帯電話を変えた。
細山が企画・編集などをしたマンガ本が携帯電話のマンガサイトで配信されることになり、マンガを見られるようにするためである。
その際、母親が90歳になり足が弱まり、固定の電話機に出るまでに時間がかかることが多くなってきたので、一番簡単な携帯電話をもってもらうようにしたいと思った。
話すだけの携帯電話を探したところ、auの機種(京セラ製)が一番簡単であったので、ソフトバンクからauに変えた。
ソフトバンクでも高齢者向きのもっと簡単な携帯電話を開発したらよいのにと思った。同じような機種がソフトバンクにあったら、ソフトバンクでもよかったのだから…。
auの機種は留守録もできるのだが表示の機能がなかったり、再生をするときに4つの番号を押す必要があり複雑で工夫の余地がある。
自分のものは新規加入であったので、デジタルテレビが見られるワンセグ機能のついた携帯電話(カシオ製)に無料でできた。
パケット通信料の定額制「ダブル定額ライト」(あまり使わなかった月は1050円)に入っても、今まで支払っていた毎月の額より安く加入できて、さまざまなサイトが見られる携帯電話になったので一応は満足している。
しかし今後、電話使用料に納得できるのかどうか、有効に活用できるのかどうかということが課題である。
なお電話番号は変えなくてすんだが、携帯メールのアドレスは@マーク以前は同じで、@以後をezweb.ne.jpと変えるだけですんだ。
ところで、『マンガ ユング 深層心理学入門』が今月11日夜からauとソフトバンクのマンガサイト「ケータイ☆まんが王国」(Bbmf社。http://v.k-manga.jp/)で配信され始めた(NTTドコモでは13日からのようである)。
同サイトはNTTドコモ、au、ソフトバンクの公式サイトで、業界第2位とのことである。
第1話は無料で、第2話から第13話は各話30円であるので、1冊360円ということになる。それ以外にデータ通信料のパケット通信料がかかる。
各話を合計したところ、1冊14,305KB(=14.3MB)になり、パケット通信料の定額制「ダブル定額ライト」(あまり使わなかった月は1050円~どんなに使っても4410円)に加入している場合、10MBで4723円~7566円になる。
上限を超えるので、上限の4410円を支払えばよい。
しかし、1冊4770円(360円+4410円)になってしまう!? (計算違いや勘違いをしていない限り…)。
まだ請求書がきていないので正確にはわからないが、残念ながらだいぶ高いものになってしまうようである!
定額制に加入していないともっと高くなるようで、今後このデータ通信料が大幅に安くなる必要性がある。
1冊や数冊しか見ない人にはかなり高い本になってしまうが、他の目的で上限の額まで使う人や多読の人には本を買うよりは安くなるともいえる!!
ぜひ、無料の第1話だけでも、試しにご覧いただきたい(定額制に入っている場合は170円~270円くらいで、未加入の場合は680円くらい)。
携帯電話では、雑誌や単行本とは異なった楽しみ方が多少できるように思う。
携帯電話での見せ方には大きく分けて4種類があるようだ。
紙芝居形式、移動(スクロール)形式、写真集形式、テキスト形式である。
主に、1コマ単位で見る「紙芝居」形式と、各頁をスキャニングした1頁の各コマをアップし移動して見ていくスクロール形式が中心のようである。
雑誌や本とは異なり1コマ1コマを見ていく紙芝居形式は、「電子式紙芝居」あるいは「電子芝居」といってもよい。
この場合、1頁全体が画面で見られるのは1コマで描かれているときだけで、文字が小さくなり読みにくいのでアップで読めるようになっている。
雑誌や本のときは各頁をざっと見てしまうが、紙芝居形式の場合は1コマ1コマを見ていくので、1コマ1コマがちゃんと描かれているのかどうかが明確にわかり、意外と漫画の質やレベルが問われているように思えた。
携帯電話は画面が小さいからとは侮れない。
校正したときより、実際の画面や文字は小さかったが、見て読んで楽しむことができる。
今後、マンガ作品との出会いが雑誌や単行本だけではなく、携帯電話でという若い人が増えてくるのかもしれない。
『マンガ ユング 深層心理学入門』は心を発達させて「心の問題」を解決することに役立つ作品であるので、若い人におおいに読まれるようになることを望んでいる。
現在、配信会社では多くの作品を配信できるように取り組んでいるようで、率直なところ、できるだけ手間やコストをかけすぎずに製作・配信をしたいと考えているようである。
細山のほうは少しでも完成度を高めて、読者に少しでもよい作品を読んでもらいたいと思っている。
「完成度の高い作品」は、多くの読者に広く長く読み継がれていくと思うからである。
そのため現在、このせめぎあいの中で、負担をかけないように工夫して次の作業を進めている。
『マンガ ユング 深層心理学入門』は単行本をつくってから、早いもので19年、文庫化されてからも10年がたつ。
しばらくぶりに読み返してみたところ、『マンガ フロイト』をつくる前だったので、フロイトについての記述が最適ではなかった個所があり、また最近「精神分裂病」の病名が「統合失調症」に変わったりしたので、文字の修正をしたいと思い一部赤字を入れたが実現されなかった。
今回は携帯電話による配信の現状や業界のことを知る機会であり、テストケースであると考え直している。
しかし購読料が安いといえども、読者からお金をいただくことなので、可能な限り少しでも良いものにしたい。
将来的には課題を解決して、さらに多くの人々に楽しんでもらえる完成度が高い作品にできたらと思う。
手がけるまでは画面がデジタル化されているので文字を簡単に修正できるものと思っていたが、「画像としてデジタル化している」だけなので、文字の修正がしにくいのだという。
パソコンの画面上で文字を修正することができないので、スキャニングをする前に直しておかないといけないのである。
多くの出版社のマンガ作品の場合のように、文字と絵を別の版でデジタル化しているのであれば文字は簡単に修正できるが、これにはコストががかかる。
携帯電話の場合でも情報量を多くすることは技術的には可能であると思うが、利用者のコスト負担が多くなることを避けて安く見られるようにするために、2つの版にはしていないようだ。
画面の解像度も画面が小さいので出版の場合より低いようで、携帯電話用のデータをそのまま印刷用にすることは難しいとのことである。
配信のための打ち合わせや作業を進める中で、出版界と携帯電話のソフト業界との違い、ギャップを感じた。
文字に対して「おおらか」なようで、最終校正をしても前に戻ってしまっていたり、変わってしまっていた。これは、出版界では考えられないことである。
初出や既出の雑誌、単行本名、出版社名や関係者のクレジットなどを入れないようにしているようであるが、出版社や関係者に対する謝辞をかねて入れてもよいように思う。
著作権や出版権などのお金や契約期間などの問題がからむからであろうが、出版社との契約期間の終了を確認したり、同意や了解が得られている場合には入れたほうがよいと思った(著作権の使用期間が切れて出版社に在庫がない場合には原則的には無料でよいのだから…)。
まだ成長をしつつある「若い業界」であるため、問題が生じないように過敏になっているためなのだろうか…?
これらは同社だけのことなのか、独立系サイト全体のことなのか、業界全体のことなのかはまだわからない。もう少し注意をして様子を見ていきたいと思っている。
なお同サイトとの出会いは、13年前に出版された科学もののマンガシリーズ、丸善コミックス全10巻(本HP、ナビ6「細山敏之のプロフィール」第2回を参照)のある巻を描いてくれたマンガ家さんの紹介による。
多くの若い人に読まれる可能性の高い作品から配信することが大切なので、『マンガ ユング 深層心理学入門』を先に配信させていただいた。
正直なところ、丸善コミックスは完成度にバラツキがあった。
現在、各マンガ家さんに原画を戻して修正・加筆をしてもらい、少しでも作品としての完成度を高めることができた作品から配信をし、多くの読者に楽しんで読んでもらえるようにしたいと思い取り組んでいる。
細かいところまでのすべての修正は携帯電話では無理なようなので、文庫化をして完成できればと思っている。
「血と汗と涙」という言葉があるが、ほとんどのマンガ家さんには汗を流して修正・加筆をしてもらっている。
マンガ家さんによっては汗だけではなく、広い意味では「血と涙」も流して取り組んでくれているようなので、それらの作品に対しては、細山も汗だけではなく「血と涙」を流しながら、工夫をして実現していきたいと思っている。
意外と手間がかかり、予定より進み具合が遅くなってしまっているが、すでに携帯配信のために3冊分の原稿は入稿済みで、近々2冊分を入稿する予定である。
関係者だけではなく、読者にも真に喜んでいただける日がくることを楽しみにしながら……。
ところで、 現在、携帯電話の使用者のうちヘビーユーザーの約4割は電話をあまり使っていないという調査結果がでている。音楽やゲームなどのデータ通信量などが増えているようだ。
「携帯電話」という名称が適当ではなくなっているように思える。
すでに電話やハガキ(手紙を含む)だけではなく、テレビ、新聞、雑誌、単行本、カメラ、時計、カード(支払い)などの機能をもち、年々、記憶容量も増えて進化してきて、すでに使い切れないほどの機能があるといってよい。
若い人たちには欠かせない必需品になっている。
新しい情報、作品、人、世界と出会える「マジックボックス(魔法の箱)」、あるいは「ミラクルボックス(奇跡の箱)」になってきている。
「マジックフォン」、あるいは「ミラクルフォン」ともいえ、新しいネーミングができるものになっている。
今回のマンガ配信を機に、今後マンガだけではなく、文字を中心としたパソコンの本ホームページと携帯電話を連動させて、その後に出版するという企画も実現して、若い人々の「心の問題」の解決、「心の発達」に役立つことができればと思い始めている。
5月15日(火)
先月10日に『マンガ 5月から読む精神分析学入門』石田おさむ・画、福島章・解説(大和書房、だいわ文庫、本体価格648円)が発行された。
同書は『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』(講談社、ソフィアブックス、1999年、本体価格1500円、本HPのナビ6 「細山敏之のプロフィール」第2回参照)を新しく編集し直して文庫化したものである。
マンガの構成では冒頭の話の入り方を変えて、福島章・上智大学名誉教授の解説をマンガの後にまとめて読みやすくしてある。
また、新しく「精神分析学・精神医学豆事典」を巻末につけて、自分や人間の心とともに心の病について知ることに役立つ内容になっている。
『マンガ 5月から読む精神分析学入門』という書名は、フロイトの名前を知らない若い女性編集者がいたようでフロイトの名前で本が売れる時代ではなくなっていること、ある出版社の本で「精神分析」という用語を使った本が売れたこと、「五月病」という言葉が使われるように五月になると心を病む人が多くなること、などからつけられた。
個人的には、具体的な時期を入れない『マンガ 悩んだときから読む精神分析学』といった一般的な書名のほうがよいと思ったが…。
表紙は、フロイトが生きていた20世紀末のウィーンで活躍したクリムトの絵が使われていて、品のよい仕上がりになった。
活字本のような装丁で、従来のマンガ本とは異なるイメージのものとなっている。
「だいわ文庫」は昨年2月に創刊されたノンフィクション・実用書系の文庫で、毎月5冊ずつくらいを発行している。
今年2月に創刊2周年を迎えたのを機に、時代小説も発行をし始めたが好評のようである。
昨年の本日記(3/21など)に書いたように、同文庫は講談社でベストセラー書を何冊もつくり、+α文庫や+α新書などを手がけた古屋信吾さんが講談社を定年になり、大和書房にスカウトされて立ち上げたものである。
一昨年の8月に古屋さんから「だいわ文庫」を創刊することになったとのお葉書をいただき、9月にお会いしたときに『マンガ フロイト』の文庫化が決まった。
その後、古屋さんから「まえがき」を書き直す案や本文の欄外に縦の注を入れるなどの案がでて原稿を書いたり、試行錯誤が続き手間がかなりかかった。
しかし結果的に、「まえがき」として描き下ろしのマンガ3ページを入れた現在の形の本になった。
一時、初校のゲラがねてしまったが、今年2月に発行日が急に決まり、3月に再校正を一気にした。1年半以上かかって実現したことになる。
途中の経過はどうであれ、できるだけ多くの読者に買っていただき読まれるようにするための工夫を、可能なかぎりしていく古屋さんの編集の姿勢には学ばせていただくものがあった。
細山の名前が原作者としてカバーにも入ればよかったが(奥付には入っている)、残念ながら実現しなかった。
9年前にシナリオの原稿を最初から最後まで一人で書き、仕上がりもほぼその通りになっていて、原作者としての実質的な「デビュー作」で、今後さらに書くことに力を入れたいと思っているので、その布石、実績としても使いたいと思っていた。
編集とライターの一人二役というのは、黒子に徹するという「正統の編集者」から見ると認めがたいことなのかもしれない…。
小生の名前では知名度がないので本が売れることにはならない、ということであったが…(売れるようにしたいものである)。
舞台裏の話はともかくとして、精神分析学はフロイトの生涯を知らずに真に理解することはできないであろう。逆に、フロイトの生涯を知ることによって、フロイトの精神分析学を真に理解することができると思う。
なぜなら、フロイトは自分の子どものころからの疑問をもとに、患者を分析するだけではなく自己(自分)を分析することで精神分析学をきずいたからである。
それを本書のマンガ部分では描き出しているので、短時間で精神分析学のポイントがわかる本になっている。
最近は中高年だけではなく、20代や30代の人にも、うつ病が増えているという調査結果が出ているが、10代でも心を病む少年が多くなり、心の発達停止、未発達、固着・退行現象などが目立つように思われる。
これを書いている最中にニュースで、福島県の会津若松で17歳の少年が母親を殺して頭部を切断しバッグに入れて警察に自首してきたことを報じ始めた。
フロイトは「動物としての人間の心」、特に攻撃的なタナトス(死の本能)とエロス(性を含む生の本能)を明らかにしているので、なぜ一般の普通の人々が殺人をするのか、その心を解明するのにも有益である。
いずれにしても本書は、自分や人間がわからなくなり悩んだときに、自分や人間の心を知り理解して、人間として心の発達をして心の病を治すきっかけにできる便利な本となっている。
なお4月下旬に、『マンガ ユング深層心理学入門』』(講談社、+α文庫、本体価格580円、本HPのナビ 「細山敏之のプロフィール」参照)が増刷(14刷、1600部)になると講談社から通知があった。
増刷は約2年ぶりであるが、早いもので元の本をつくってから19年、文庫になってから10年がたつ。
地味ではあるものの、まだ少しずつ読まれていることは大変に嬉しいことである。
上記のフロイトとユングの文庫本を一緒に多くの人々に読んでいただき、自分と人間の深層心理を理解して人生を有意義に生きることに役立ててもらえればと思っている。
また、『サイコー! セラピー』(本HPのナビ6「細山敏之のプロフィール」第2回参照)が韓国で翻訳されることになったようで、4月上旬に双葉社から通知がきた。
同書は4年前に、台湾ですでに翻訳されている。
通知の書類には双葉社への入金額3600円と原作料の864円のみで、発行部数、定価などが書かれていないのでわからないのだが(3000部くらいであると思うが)、ロイヤルティが安すぎるように思われる。
アジアの場合、他の国でも出版部数が少ない場合が多いので、版権使用料は数千円~数万円レベルが多い。しかし、韓国の経済力、物価のレベルからは、もう少し高くてもよいと思う。
いずれにしても、金額はわずかでも他国で翻訳されることは喜びである。
同書も5年がたったので、そろそろ文庫化できて、さらに多くの日本の若い人に読まれるようになればと思っている。
2月11日(日)
昨年の暮れに、学生時代の友だち、荻原光雄、作田稔、竹間忠夫、高橋次朗くんと一緒に飲んだ。
そのとき、経済ジャーナリストとして活躍をする竹間くんから著書『ドキュメント JC東京ブロック協議会』(アールズ出版、定価=本体1500円+税、2006年11月刊)をいただいた。
JCとは日本青年会議所の略称で、20歳から40歳までの青年経済人の団体である。日本商工会議所の弟分にあたる。
その東京ブロックの人たちの活動を取材して、現在進行形のスタイルでまとめた本である。
彼らが取り組んでいる問題は、政治、憲法、行政、経済、教育、環境問題などと幅広い。
同書の構成は第1章~第6章からなり、それぞれ「変貌を遂げる東京ブロック協議会、東京ブロックを“運動体”に、国を変える運動と連動せよ!、公開討論会の開催は当たり前だ!、市民討議会を全国に!、彼らは日本を変えられるか」というものになっている。
最近、町や地域起こしの必要性が生じている。同時に、関心をもつ人も多くなっている。
同協議会のユニークなところは、「東京を変えて、日本を変えたい」という志をもち、活動をしていることであろう。
深層心理学者のアドラーは、社会に貢献をしようという「共同体感覚」をもち行動することは劣等感を克服して、心の病を治すことに効果があることを指摘した。
つまり、「心の発達」に役立つのである。
いまの東京を、あるいは日本をよくしたいと思っている人だけではなく、いままで自分のことにしか関心をもたなかった人にも、ぜひ同書をお薦めしたい。
ところで、話はまったく変わるが、今年1月に歯科医を志望する浪人中の兄が妹を殺して死体を切ってバラバラにしたり、妻が外資系の会社員の夫を殺して死体を切ってすてるという悲惨な殺人事件がたてつづけに起こった。
一般の常識的な考え方からすると、「なぜ妹や夫などの身内を殺して、しかも死体を切ってバラバラに……」「信じられなーい」ということになるであろう。
兄は妹に、妻は暴力をふるった夫に激しい怒り、憎しみをもったようである。
死体をバラバラにするということは、それだけ憎悪の念が強く、相手を抹殺したいと思ったからであるというのが、犯罪心理学の説である。
本「日記」(昨年12月14日)で、フロイトが「タナトス=攻撃的な死の欲動(本能と訳されることもある)」は誰でもがもっていること、つまり誰でもが殺人や自殺をする可能性があり、「動物としての人間は危険な生き物である」ことを指摘したことについて書いた。
もう一つ、この殺人事件を読み解くときに参考になるのが、フロイトが重視した言葉「アンビバレンス(両価性)」である。
「アンビバレンス(両価性)」とは愛と憎しみの矛盾した感情を生じることである。
この言葉を応用して考えると、身内であればあるほど、このアンビバレントな感情が生じやすい。
つまり、兄は妹を、妻は夫を愛していたがゆえに、自分を否定した言葉や行動に激しい憎しみをいだいたのである。
その憎しみの感情が「タナトス=攻撃的な死の欲動」の引き金になり、兄は妹を、妻は夫を殺して、死体を切りバラバラにしたと解釈ができる。
では、こうした殺人事件が生じないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
解決するための結論は、難しいようで意外と簡単である。
「心の発達」ができれば、殺人はしないのである。
しかし、この「心の発達」はやさしいようで、意外と難しい。
心が発達して、「他者、共同体のために貢献をしよう、自分の生命を捧げたい」という段階になっていれば、殺人をすることはないであろう。
人間の「心の発達」の最高の段階は、「慈悲(抜苦与楽)」、「アガペー(無私の愛)」の心をもって、実践をして生きている人の心である。
この段階は「真の宗教者」、つまり「聖人」や「菩薩」の心の段階であるともいえる。
無心に他者のために生きていれば、すでに無我になっている。
無心、無我であれば、自我・己(おのれ)の心がないために、心の病にもならない。
その発達途上にわれわれ人間の心はあるが、この最高の段階に達していなくても、「人に迷惑をかけない」「自分のできる範囲で人のためになることをしよう」などという考え方をもっていれば殺人はしない。
しかし、殺人をした二人は自己愛が強すぎて自己中心的になり、残念ながら自分のことしか考えられない心の状態になっていた。
自分の感情にまかせて、自分が満足するために行動をしてしまった。
いや「タナトス=攻撃的な死の欲動」に心を支配されて、行動せざるをえなくなってしまっていたといえる。
二人が他者、「共同体」のために行動をすると心に充実感がもてることを知っていたら、彼らの運命は違っていたであろう(これは殺人をした二人だけの問題ではなく、われわれにも共通した問題である)。
現在の日本では、アドラーのいった「共同体感覚」が非常に弱くなっている。
冒頭でふれた竹間くんの著書『ドキュメント JC東京ブロック協議会』は、東京のみではなく日本という「共同体」のことを考えて行動し、「心の発達」をしつつある人たちのドキュメント、一つのケーススタディの書ともいえる。
ビジネスや地域起こしに関心のある人だけではなく、一般の人々にも有益である。
広い意味で「心の発達」にも役立つ同書を、ぜひ、お読みいただければと思う。
今日は「建国記念の日」である。
偶然、タイミングのよい内容になったと思う。
あるいは、ユングの指摘した「共時性=シンクロニシティ(直接の因果関係がわからない心理的な平行現象)」ともいえる。
いずれにしても、この日の意味や神話について考えることは、「共同体感覚」だけではなく、ユングがいったように深層心理学的に意味があり、「心の発達」に役立つ…。
1月1日(月)
明けまして、おめでとうございます。
い(亥)い年になりますようにお祈りいたします。
現代の日本において(あるいは世界的にみても)、少年や青年にかぎらず大人にも心の発達停止、未発達、固着・退行現象などが目立ちます。
「心の発達」ができれば、いい生き方ができて心の病(自殺、殺人を含む)は治り、あるいは心の病にかからなくなりますので、今年は自他の「心の発達」に役立つことをし続けて、社会、人々におおいに貢献できるようになればと思っています。
具体的には、まず単行本『仮想「深層心理楽(がく)」読本(or超入門)』の原稿を早く仕上げて出版できるようにすることと、本HPの充実ということになります。
『仮想「深層心理楽(がく)」読本(超入門)』は、専門家の書いた本とは異なって「遊び心」があり、やさしく読めて心が楽しくなる広い意味での「娯楽書、エンターテイメント本」です。
早く仕上げて、次の本に取り組めるようになればと思っています。
本HPについては、ソフト「ホームページ・ビルダーV9」をバージョンアップした「V11」が発売されたようなので、購入して改定できればとは思っていますが、まずは上記の本のことを優先させたいと思っています。
それゆえ、本HPのほうは各ページを少しずつ更新し、内容・中味を充実させていくことになります。
本HPの特徴と意義は、人のためにもなり、自分のためにもなることだと思います。
昨年、一般向けの心理学(楽)雑誌の企画書をつくりましたが、長期的には、そのアイデアを本HPの中に取り入れて、バージョンアップをし続けて雑誌的な独自のHP(メールマガジン?)にしていくのがよいと考え始めています。
もちろん紙媒体とは異なり、インターネットならではの展開の仕方にはなります。
たとえば、まず関連するサイトと連携・リンクしたウェッブサイトにすることなどが考えられます。
上記以外には、詳細はまだ書けないのですが、昨年の「日記」を更新した後に、二つの新しい動きがありましたので、その動きに応じて動いていければと思っています。
一つは、広告会社の千崎さんから電話があり、新しい形でまた本が出せるようになるので、協力できるかどうかの打診がありました。
「言葉の力」シリーズで考えたことの一部が実現できるかもしれません。
もう一つは、浜野さん(本日記,10月17日など参照)からで、小生が企画・編集したマンガ本の一部について電子本と携帯電話への配信を了解してくれれば、ある社で検討したいという話がでているとのことでした。
せっかくの機会ですので、ご検討をお願いしました。
いずれも決まってみないとわかりませんが、時代と社会が大きく変化しましたので、既成の考え方にとらわれずに柔軟に対応して、読者に真に楽しんでいただけるものにできればと思っています。
上記以外には、『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』の文庫が早く出版されることと、今年はフランクル、アドラー、エリクソンなどのマンガ化の企画が決まればいいなと思っています。
読者に喜ばれて売れる本とするには、ページ数を多くせずに、定価を1000円以下にすることと、実用的で楽しめる内容にするのがポイントだと思っています。
自然に四季があるように、人生にも四季がありますが、個人的にも冬の季節に入っていましたので、忍耐、我慢の日々が続いています。
新しい芽が出つつあるようなので、水をやって(自分のできることをコツコツとして)育てて春の花を咲かせて、夏と実りのある秋を迎えて充実した年にできればと思っています。
本年も、よろしくお願いいたします。
トップページに戻る
2006年(平成18年)
12月14日(木)
(注) ソフト「ホームページビルダー9」にワードの文書から文字データを呼び込んだところ、文字間のアキがあきすぎていたり、書体の変更の操作をしても明朝体からゴシック体に変わらないなど、満足できない文字組になってしまいました。
読みにくい場合には、ご了解のほどよろしくお願いします。
時間がたつのは早いもので、もう12月中旬になり、今年も残りわずかになってしまった。
いじめによる自殺などがマスコミで多く報道されている。
細かいことはフォローをしきれていないのだが、岐阜県の中学校の同級生によるものに始まり、福岡県の中学校における教師によるもの、あるいは千葉県や鹿児島県の中学校では校長による教師へのパワーハラスメント(上司による嫌がらせ)なども生じている。
これらのことは一部の県の出来事ではなく、全国的に同様のことが生じているようである。
いじめではないが、高校の必修科目の履修漏れ問題で、校長が2人自殺をしている。
なぜ、いじめといじめなどによる自殺が生じるのであろうか?
深層心理学的に考えてみると、動物としての人間は自己保存をするために、自己愛が強く自己中心主義的で、自分を優位にして生きようとする。
いじめている人間は「弱肉強食」的に生きている。正確には、いじめている人間も弱者のようで、弱者が弱者をいじめているという現象のようである。
また頭や意識では、いじめをしてはいけないとわかっていても、弱者であるがゆえに優越感を持ちたいという「無意識」が働いて、いじめてしまっているともいえる。
一方、いじめられた人間の心には「劣等感」(アドラー)が増して絶望をし、「生きる意味」(フランクル)を失ってしまったのだと思う。
客観的に見ると、何も自殺しなくてもと思うが、自殺者の心の働きは狭くなり、自殺が唯一の行為だと思ってしまう。
いじめる者といじめられた者は表裏一体の関係にある。いずれの側の者にも心の発達停止、未発達、固着・退行現象があったわけで、心を真に発達させることができれば、いじめや自殺はなくなる。
フロイトは人間の心の無意識には「タナトス(攻撃的な死の欲動)」と「エロス(性を含む生の欲動)」があるとしたが、自殺は「タナトス(攻撃的な死の欲動)」を自分に向けて行動したものといえる。
いじめられていなくても、自分が不利な状況に追い込まれたときの自殺についても同じことがいえる。
フロイトの「タナトス(攻撃的な死の欲動)」は、自殺者やいじめた人間だけに生じるわけではなく、すべての人間の心の中に生じるものである。
そのため、誰にでも自殺をしたり、いじめる側の者になる可能性はある。
普通の人間は、自殺をしたり、いじめをすることは自分や家族、友達などのためにも、また社会的にみても現実的ではないと思っているからしない。
あるいは「エロス(性を含む生の欲動)」が強いため、自殺をしないで生きているともいえる。
人をいじめることより、「人を愛する」ことのほうがすばらしいことで大切であるが、彼らはこのことに気づいていない。
「人を愛する(ラブ、アガペー、慈悲)」ということは高度の人間の「知恵」でもあるが、それがわかり心を発達できるように手助けをする必要がある。
そのためには、学校で「心の教育」が行なわれるようになることが望まれる。
なお、自殺は「タナトス(攻撃的な死の欲動)」を自分に向けて行動したものであるが、他者に向けて「タナトス(攻撃的な死の欲動)」を行動にうつしたのが殺人である。
ある意味で、殺人もあらゆる人間がする可能性があるのである。
最近、日本国内では「人を殺してみたかった」という動機による殺人事件が何度もおこっている。
大阪の姉妹を殺した犯人(23歳)に死刑の判決が12月13日にでた。彼は16歳のとき母親を殺して快感をもち、また味わいたかったので殺したという。
こうした殺人事件は残念ながら今後もおこると思うが、フロイトが現在の日本に生きていたら、自らの理論が実証されていると思うであろう。
また、日本国内だけではなく、戦争や自爆テロなども、「タナトス」の発現といえる。
この「タナトス」に対処するには、つまり自殺や殺人を少なくするには「人間が危険な動物である」ことをまず自覚して、心を発達させて「エロス」を「愛(ラブ、アガペー、慈悲)」に昇華させて生きていけるようにすることが大切である。
しかし現在の日本では、この「愛(ラブ、アガペー、慈悲)」が男女関係に限らず、家庭や学校、社会全体において、弱くなっているのであると思う。
「弱肉強食的な国、日本」になっている中で、自殺や殺人を少なくして、「美しい国、日本」にするためには、心を発達させることのできる「愛(アガペー、慈悲)のある国、日本」にする必要がある。
教育問題では「個性」を重んじる教育から「共性(共生)」を重んじる教育、愛国心だけではなく「愛人類心」(アドラーの「共同体意識」を拡張)を重んじる教育に、発想自体を変えたり広げることが大切だと思う。
これは、日本の少子化問題を解決することにも役立つであろう。
個人的に今年を振り返ると、まず本ホームページを充実できなかったのは残念であった。
いろいろ書きたいことはあるのだが、時間がとれずに書けなかった。長い目でみて、つくっていきたいと思う。
本HPがいじめにあった高校生に役立ったようなので(ナビ5参照)、社会的な意義や役割を実感することができたのは収穫であった。
仕事面では知り合いの編集者や広告関係者から何か企画がないかと声をかけられたので、心理ものの一般雑誌の企画や、単行本の「言葉の力」シリーズ、『マンガ
深層心理学 超入門』全3~5巻の企画書をつくった。
しかし、企画は残念ながら諸事情で決まらなかった。
必ずしも企画がよくないからというわけでもなかったので、相性の合う編集者や版元さんなどとの出会いの中で、面白さと完成度を高めて、いつか実現できるようになればと思っている。
新しい「夢」を与えてくれたものとポジティブに考えている。
上記の企画書をつくることに、予想外に時間がとられてしまった。
しかし、企画書をつくるなかで、前から書き始めていた心理ものの本の切り口と構成を、遊び心のある『仮想「深層心理楽」読本(or超入門)』などとすると、専門家の本とは異なる「楽問(がくもん)」の本(娯楽本、エンターテイメント書)にできるという「ひらめき」を得られたことは収穫であった。
この「ひらめき」を生かして、原稿を書き直したり、新たに書きはじめている。
なお、『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』の文庫化は遅れていて、来年の3月か4月になってしまうとのことであった。初校が終わっているので、ボツになったわけではないということである。
そろそろ(早く!?)出版していただければなーと思っている。
岩波書店の『フロイト全集』(全22巻+別巻1)の刊行が先月から始まったが、上記の「タナトス」の考え方にかぎらず、フロイトの精神分析学には現代の日本人がかかえる心の問題を解決するための有益な考え方が他にもある。
ただ彼の仕事量は膨大で、名文家と評価されたが、一般の人が彼の著書を1,2冊読んでも彼の全体像や各論がすぐにわかるようには書かれていないので、「冗長に感じられる」のが難点である。
国際的に脳の神経科学からも見直されていて、「神経精神分析学」が発達してきている。
他には、入居しているマンションで空調や温水関係の工事が始まり、部屋に空きスペースをつくって来年3月までに工事をしてもらう必要性が生じている。本や書類などがたまってしまったので、部屋の整理・掃除をして不要物の処分などもしている。まだ時間がかかりそうである。
今年は、これが本HPの最後の更新になる。
来年は、社会、人におおいに貢献できる良い年にできればと思っている。
本年は愛読していただき、有難うございました。
まだ早い気がしますが、良いお年をお迎えください。
10月17日(火)
パソコンや携帯電話などで読める電子書籍の売上げが2004年から急激に伸び、2005年は約2倍になり、約94億円になったという。
特に、2003年からの携帯電話による利用の伸びが著しいようで、2005年には電子書籍のほぼ半分を占め、20代、30代の働く女性の利用が急増し、コミックものが売れているようだ。
単行本より100円以上安い額で見られるようになっているという。
電子書籍関係のことで、友だちから声をかけられたことが二度ある。
一度目は8,9年くらい前で、丸善コミックスのシナリオを書いてくれた友だちからである。
彼が属していたライターの団体の主催者が電子書籍をつくる組織と関係ができ、企画を求めているので会ってみないかということであった。
そのときは、丸善コミックス全10巻を出してから3,4年くらいであることや、時期尚早かと思い、紹介をしてもらわなかった。
二度目は今年8月で、ミュージシャンの本多信介さんからである(彼のHPのアドレスは本HPの「ナビ10」参照)。
細山が企画・編集などをした『マンガ ユング 深層心理学入門』のプロローグをデジタル化してくれて、パソコンで見られるように「試作品(デモバージョン)」をつくってくれた。
同書の各頁を単にスキャニング(コピー)しただけではなく、各頁のコマをわけて、パソコンで見られるように工夫がしてあった。
この形式であれば、携帯電話でも見られるものとなる。
ただし、文字は本の文字をコピー(スキャニング)しただけであったので、文字の大きさを画面の大きさに応じて変えられれば、さらによくなると感じた。
お礼と電子書籍が現実的になってきたことを感じる旨をメールしたところ、電子書籍関係の仕事をしている浜野智さんと会わないかとのことであったので、紹介をしていただき、三人で9月中旬にお会いして飲みながら話をした。
浜野さんは出版関係の編集プロダクションの会社をもち、企画・編集・取材・原稿作成・DTP組版など、幅広く仕事をされている。
特に音楽関係の造詣が深いようである(同氏のホームページは本HPの「ナビ10」参照)。
電子書籍関係の仕事では、ソフト会社のボイジャー(http://www.voyager.co.jp/)やドットプレス(https://www.dotbook.jp/)の仕事をされているという。
ボイジャーでは現在、講談社のコミック数百点を電子書籍化する仕事をしていて、同社の方法ですると、かなり安いコストで実現化できるようである。
機会があれば、細山が電子書籍化、特に携帯電話でも見られるようにしたいと思っている企画に二種類ある。
一つは、丸善コミックス全10巻である(本HP、ナビ6「細山敏之のプロフィール」を参照)。
ダ・ヴィンチからガリレオ、ニュートン、ダーウィン、アインシュタイン、カーソン、ワトソン、クリック、そしてホーキングまで13人の科学者などの自然や宇宙との出会い、生きた姿を通して、彼らの考えたことや科学の世界、ロマンを楽しめるマンガ本である。
もう一つは、『マンガ ユング 深層心理学入門』(理想社、講談社+α文庫)、『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』(講談社)、『サイコー! セラピー』『ご開帳! 聖天さま』(ともに双葉社)などの心理ものである。
一つ目の丸善コミックス全10巻は1994年刊であるから、早いもので12年がたったことになる。
当時は、科学・技術に対する人気がなくなり、「逆風」が吹いていた。
現在、政府や科学技術者などは人気を挽回するために、さまざまなイベントなどをして、青少年に科学技術が理解されて興味をもつ人が増えるように努力している。
丸善コミックス全10巻は、文庫化しながら、電子書籍化ができればと思っている。
文庫化のときにデジタル化すれば、それを「加工」して、パソコン、電子書籍用の端末、携帯電話のいずれでも見られるようにできるからである。
全10巻中の2巻は文庫化されたことがある。
『コミック ホーキング』は1997年に朝日新聞社の朝日文庫で(『コミック ホーキングの宇宙論入門』と改題)、『コミック アインシュタイン』は1999年に講談社の+α文庫でなった(『マンガ 誰にもわかる人間アインシュタインと相対性理論』と改題)。
いずれも現在、品切れ(絶版)になっている。
当時、全10巻のうち5,6巻は朝日文庫で文庫化できることになったが、文庫『マンガ ユング』の売れ行きが好調で講談社+α文庫から「うちで文庫化しないか」と誘ってくれたので乗りかえてしまった。
ところが、『マンガ フロイト』など細山の企画を担当してくれていた女性編集者の本づくりに納得ができずに不満を持ってしまい、残念ながら細山が講談社へ行かなくなってしまったので、1冊は文庫化されたものの企画が途中になってしまった。
上記の2社に話をすることには無理があるが、科学ものに関心、理解のある出版社で文庫をだしている出版社との出会いがあればと思っている。
筑摩書房さんか学研さんなどがよいのかなと思っているが、細山はまだ両社に知っている人はいない。
細山が直接、電話をして会っていただくことも考えられるが、その準備を含めて、そこまでは現在 時間を取ることができない。
現在、日本人にとって科学・技術の振興や科学的な考え方の普及も大切だが、もう少し機が熟するのを待ってもよいのかなと思っている。
なお、先に電子書籍化だけをすることも考えられるが、その場合はコスト負担などをしてくれる電子書籍のサイト(版元)があればしたいが、細山がコスト負担をする形態は現在のところ考えていない。それだけの金銭的、時間的余裕が、まだないからである。
ところで現在 日本では、いじめ、虐待、親・子ども・性嗜好異常者などによる殺人がおこったり、自殺者が年間約3万人という問題などが生じている。最近では、30代でうつ病や神経症などの心の病になる人が急激に増えている(社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所の調査結果)というように、緊急を要する大きな問題は「心の問題」であると思うので、このジャンルに時間やエネルギーを注いでいきたいと思っている。
若者を含めて われわれ大人にも、「心の退行現象」だけではなく、「心の発達停止現象」や「心の未発達現象」などが、はびこり広がっているのではないかと、細山は思い始めている。
もちろん、これは日本だけの問題ではなく、世界的な問題であるともいえる。
「心の発達」ができれば、心を病まずに、また人と争わずに、健康で平和的に楽しく生きられるのであるが、心が退行・発達停止・未発達であると心を病み、人と争い対立して、不安を感じイライラして不愉快に生き、死ぬことになる。
楽しみながら「心の発達」に役立つのが、『マンガ ユング深層心理学入門』(理想社 1989年刊、講談社+α文庫 1997年刊)、『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』(講談社 1999年刊)、『サイコー! セラピー』(双葉社 2002年刊)『ご開帳! 聖天さま』(双葉社 2005年刊)などの心理ものである。
この心理ものは、仮に「硬派」と「軟派」の二つの路線にわけられる。
「硬派」の路線が、『マンガ ユング』、『マンガ フロイト』である。また、「軟派」の路線が、『サイコー! セラピー』『ご開帳! 聖天さま』といえる。
『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』は改題・再編集して、大和書房の「だいわ文庫」から、この秋に出版される予定であったが、企画が目白押しのようで、12月か来年1月になるとのことである。
同書は、すでにデジタル化されているので、電子書籍化や携帯電話での配信がしやすい状況にはある。
もちろん、その利用には版元さんへ依頼して話し合いが必要になる。
現在、「硬派」の路線では従来の「アナログ形式の出版」で、新たな企画を準備中である(製作過程はデジタル化されると思う)。機会があれば「軟派」の路線の企画も手がけたいとは思っている。
いずれにしても、このジャンルはマンガにかぎらずに、活字の単行本でも今後さらに企画を充実したい。
「軟派の路線」の2冊も、文庫化ができればと思っている。
『サイコー! セラピー』『ご開帳! 聖天さま』は残念ながら初版だけであるので、双葉社での文庫化は難しいと思われる。
『サイコー! セラピー』『ご開帳! 聖天さま』の製作過程はアナログ形式であるが、文庫化するときにデジタル化をして、電子書籍化すれば効率がよく生産性が高まる。
いずれにしても、電子書籍、特に携帯電話での配信の最初の「突破口」としては、『マンガ ユング』がよいと考えている。
なぜなら、心の病は「真の自己実現」ができていないからで、「真の自己実現」・個性化ができれば治るというユングの考え方は、心の退行・発達停止・未発達現象を含めて、あらゆる心の病に有効であるからである。
また、ユングは女性にも人気があり、『マンガ ユング』は出版部数の実績もあるからである。
もちろん、同時にパソコンや電子書籍の端末で見られるようにしてである。
『マンガ ユング』はいままでのアナログ形式の印刷方法でしてあり、デジタル化はしていないので、その費用や携帯電話用のソフトによる製作費がかかる。
それを細山が負担する自費出版的な方法ではなくて、それを負担してくれて、多くの若い人々に読まれる可能性のある人気のあるサイト(版元)で実現できればと思う。
もちろん、マンガの形式ではあるが、コミックの本流の企画ではないので、コミックのサイトではなく活字の電子書籍を配信しているサイト(版元)でもよいのかもしれない。
いずれにしても、デジタル化するからには、パソコン、端末、携帯電話のいずれでも見られるようにしたい。
話は少し変わるが、単行本の製作段階がデジタル化されてきたので、アナログ形式の本の出版とデジタル形式の電子書籍の発行を同時にする出版社も出てきたようだ。
細山が今後する仕事でも、マンガにかぎらず、活字本と電子書籍との連動が可能になってくるような気がする。
そのためには最初から多くの読者に読まれることを意識したテーマ・企画で、多くの人々の心に響く内容であることが必要である。
「一家に一冊」というより、「一人に一冊!」必要となるものである。
いまはまだ電子書籍の仕事をメインにすることはできないが、可能であれば今後 少しずつタイミングを見はからって、出版社の編集者や関係者などに話したり、了解を得るようにしたいと思う。
ブログのヒット作などが単行本になり売れるというように、「デジタルの世界」の長所を生かしながら展開をして「アナログの世界」に連動すると成功する例が出てきている。
携帯電話への配信を含めての電子出版、電子書籍を中心にしながら、その一環として、アナログ形式の出版もするというような「電子出版社」が可能になってきているのだと思う。
もちろん、それなりの手間、コストなどがかかるので、採算性をとれるようにすることが大切であることはいうまでもない。
従来のアナログ形式の出版に頼らずに、アイデアと内容次第では電子書籍だけでもなりたち、成功する可能性がでてきているわけである。
たとえば仮に細山の場合、現在のホームページの一部を特化して発展させたものや別の企画で、多くの人々が有料でも読んでみたいというものがつくれれば、それは「電子書籍」になる。
それで、あるいは広告収入などで成り立てば、「電子出版社」ができる。
これらのことは、次の「新しい夢」として、今後、検討をして工夫していきたいと思う。
以上、本多さんのメールを機に、「電子書籍」や「電子出版社」などについて考えることができた。
しかし、上記のことは短期間で多くの点数の企画の実現(自費出版形式)を望まれていた浜野さんの意にそえないものであるような気がしている。
立場の違いもあるので、長い目で見ていただき、ご了解をいただければと思う。
9月10日(日)
フランクルの伝記、『人生があなたを待っている <夜と霧>を超えて』1,2(ハドン・クリングバーグ・ジュニア著、みすず書房、2006.6.22、各本体2800円+税)と、『アドラーの生涯』(エドワード・ホフマン著、金子書房、2005.8.29、本体7400円+税)を読み終わった。
いずれも詳細は、本HPのナビ1,2,3,7などで書きたいと思っているが、フランクルやアドラーについて、また深層心理学について知りたいと思っている人、自分の心の世界を広げ深めて悩みごとや心の病を解決して、人間として成長をしたいと思っている人などには、ぜひお薦めしたい本である。
『人生があなたを待っている <夜と霧>を超えて』は、1993年から7年間にわたってフランクル夫妻などを直接取材して書かれた本である。
『フランクル回想録』(春秋社、1998.5.15、本体1700円+税)とあわせて読むと、「人間フランクル」を理解でき、「ロゴセラピー」が生まれた経過や時代背景などもわかる。
この本のユニークなところは、まず書名『人生があなたを待っている』と内容構成(章立て)であろう。
フランクルは4歳のときから「人生の無常さ」について悩んでいたが、15,6歳のときに「われわれは人生の意味を問うべきではなく、われわれが人生からの問いに答えるべきなのだ」と気づき、悩みを解決することができた。
この考え方の延長にあるのが、「人生があなたを待っている」という言葉である。
フランクルはユダヤ人強制収容所の中で、具体的に「『本(著書)を出版すること』が自分を待っている」「妻が自分を待っている」などと考えて生き抜くことができた。
同時に、彼は収容所の中で絶望をして自殺願望をもっていた人に、本人の「人生」において「恋人、妻、仕事、趣味」など、大切な人、ものを気づかせて救っている。
フランクルは早熟で、16歳のときにフロイトに手紙を書き2年間 文通をして、18歳のときにはアドラーの個人心理学会に入会をしている。
しかし、24歳のときにアドラーから退会させられて、その後、独自の「ロゴセラピー(意味による癒し)」をつくった。
先ほどのフランクルの「人生があなたを待っている」という言葉、考え方に出会ったときに、細山は最初さほど感動をしなかったというのが、正直なところである。
しかし、宗教的なことにも関心のある細山は、彼の言葉は「神(あるいは仏)があなたを待っている」に通じていると気がついたときに、「ああ、なるほど!」と思った。
つまり、「われわれは、神(あるいは仏)に何かを望むのではなく、神(あるいは仏)または人々(あるいは社会)に何ができるのかを問うべきである」ということである。
同書の内容構成は三部からなる。
第一部がフランクルの誕生からユダヤ人強制収容所での両親と最初の妻ティリーの死、開放まで、第二部は二番目の妻となったエリーの誕生からフランクルに出逢うまでの生活など、第三部がフランクルとエリーの出逢いから結婚、二人が協力して「ロゴセラピー」の完成と普及に取り組んだことや、二人の日常生活、生き方など、という構成になっていることである。
フランクルは、それまで著書や取材、講演でも、妻や家庭、宗教などのプライベートなことについてはほとんど書いたり語らなかったが、この本のために語り、妻のエリーを「もう一人の主人公」として尊んで本がつくられている。
フランクルは1946年41歳のときに、二番目の妻となる20歳のエリーと出逢い同棲を始めて、翌年に結婚をした。
しかし、フランクルが信仰をしていたユダヤ教ではカトリックの女性と結婚することは認めず、またエリーのカトリックでも異教徒との結婚は認められていないのだという(死んだときも一緒のお墓にはいることはできない)。
さらに、前妻ティリーのユダヤ人強制収容所での死亡通知がきていない中での結婚であったので、祝福されなかったという。
妻エリーは子どものときは「おてんば娘」で、天真爛漫な明るい性格だった。
ユーモア好きのフランクルとの会話はざっくばらんで、他の人から見るとケンカをしているように見えることもあったようだ。
フランクルは亡くなる前に、エリーに1冊の本を残したと言う。
彼の死後、エリーが探すと、フランクルの著書『苦悩する人間』で、その冒頭に、「エリーへ あなたは、苦悩する人間を愛する人間に変えてくれました。ヴィクトール」と書いてあった。
これはもちろん、エリーがフランクルを「愛する(ことができる)人間」に一方的に変えてくれたという意味ではなく、エリーがいてくれたおかげで、フランクルが「愛する(ことができる)人間」になれたことを感謝した言葉である。
お互いに「愛する(ことができる)人間になる」ことが、異性と出逢い、結婚して、生きることのもう一つの真の意味であると思う。しかし、これがなかなか難しい…。
フランクルの場合、広い意味では妻だけではなく、多くの人々を愛し助けて精神科医として生きたことは言うまでもない。
本書は、フランクルの伝記であるとともに、宗教の異なる夫婦二人が協力をしあって生きた真の「愛の物語」でもある。
フランクル夫妻は、本HPのナビ7「『男と女』の関係の10段階説」の第8段階「理想的な最高のカップル、夫婦の状態」(お互いの「個人史」の愛情不足・過多・ゆがみを補い合う「和合」ができトラウマが治せる)といえる。
男と女の関係、結婚(離婚を含む)、人間の生と死、人生などについて考えたり、あるいは考えを深めたいと思っている人にも本書をお薦めしたい。
もちろん、フランクルの『夜と霧』『死と愛』(いずれも、みすず書房)とあわせて読むと、フランクルの人間としての「心の広さと深さ(高さ)」「愛の広さと深さ(高さ)」が理解できる。
『アドラーの生涯』は、日本では初めてのアドラーの本格的な伝記である。
アドラーの著書(邦訳)の中にある彼についての簡単な生涯の説明では物足りなかったが、ようやくアドラーの生涯や家族などについて、日本語で知ることができるようになった。
アドラーはフロイトと1902年から9年間一緒に研究をしたが、フロイトの考え方に同意できずに、独立して「個人心理学」をつくり活躍をした。
アドラーのすばらしさは、「劣等感(コンプレックス)」が神経症、非行・犯罪、自殺などの原因で、「共同体意識」をもって人々・社会に貢献する生き方ができれば心の病は治ると、単純明快に明らかにしたことである。
アドラーの妻ライサはユダヤ系ロシア人で、ロシア革命で活躍した共産主義者トロッキーのシンパであったという。
アドラーは「男女は平等」と考えていて、女性の権利・人格を認めていた。
彼は社会主義者であったが、暴力による革命は否定をしていた。
アドラーはフロイトとはタイプが異なり、行動派で、1935年にアメリカへ移住した。1937年にイギリスへ講演旅行に行ったとき、スコットランドのアバディーンで心臓発作を起こし67歳で亡くなった。
フロイトなどは論文を書くことにも力を注いだが、アドラーは実践派で、講演の筆記を起こしてまとめた本がほとんどである。他の深層心理学者と比べると短命でもあり、著書の数が少なかったことが惜しまれる。
ところで最近、日本では北海道の高校1年生が母親を殺したり、山口県の高専生が女子の同級生を殺して自殺をするという悲惨で気の毒な事件がおきてしまった。
残念ながら、こうした事件は、これからも多くおこってしまうであろう。
また、自殺者が年間約3万人という問題だけではなく、最近は30代でうつ病や神経症などの心の病になる人が急激に増えているという(社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所の調査結果)。
アドラーとフランクルは、多くの自殺願望者を救ったり、非行・犯罪者を改心させることにも貢献したが、フロイトなどを含めて、細山が本HPで取り上げている「深層心理学の5巨人」は、現代の日本人がかかえている「心の病」などを解決することに非常に役立つ。
現代の日本人がかかっている心の病や問題をどうしたら解決できるのかをアドラー、フランクル、フロイトに質問すれば、次のように単純明快な答えがかえってくると、細山は思う。
アドラーであれば、「彼らは『劣等感(コンプレックス)』をもっているので、『共同体意識』をもち人々・社会に貢献できるような生き方ができるようになれば、すべてを解決できます」というであろう。
フランクルであれば、「彼らは人生に意味を見い出せずに、『むなしさ(実存的空虚)』を感じているので、『人生の意味』が発見できれば、すべてを解決できます」というであろう。
また、フロイトであれば、「彼らは『生[性を含む]の欲望(エロス)』が抑圧されて満たされていないので、愛と憎しみのアンビバレントな(両価性の)矛盾した感情を生じて、攻撃的な『死の欲望(タナトス)』が意識にのぼり、殺人や自殺をしたり心の病になっています。『エス(生[性を含む]と死の無意識の衝動)・自我・超自我』からなる心のバランスをとり、現実に適応できるようになれば解決できます」というであろう。
そして、三人とも「わたしの理論は人間の心を見えるようにするライト(灯り)と同じで、それを使って日本のマスコミが騒いでいる『心の闇』を見れば、『心の闇』はなくなります! 心は複雑なようで単純なのです!!」というであろう。
アドラー(1870.2.7~1937.5.28)、フランクル(1905.3.26~1997.9.2)、フロイト(1856.5.6~1939.9.23)の三人は同じウィーンに住み、出会っている。
しかし、自分の考えていること(理論)が正しくて、他は誤りだと思ってしまい、仲が悪くなり、疎遠になってしまった(彼らが、自説をつくった動機、子ども時代の疑問などについては、本HP、「ナビ3」第1回[2005.7.4]を参照)。
それぞれが残念ながら自分の説だけが正しいとして、他者の説を否定した(「自説肯定、他説否定」)。
また、それぞれを支持する専門家であれば、自派の説をとりながら、その一部を修正しながら発展させたりするであろう(「自派肯定、他派否定」)。
しかし、「専門家」ではなく、しがらみをもたない「一ライター(一人の人間)」としての細山は、「すべての説は正しいのだ!」と、大胆に「全肯定」をしたい!!
なぜならば、一人の理論だけですべての人間の心理現象をすべて説明・理解できるというわけではなく、多種多様な人間の心理現象の一部、あるいは一面をまだ理論化しているにすぎないと思うからである。
また、だれの理論、精神療法であれ、実際に患者を治して実証している場合には、「それなりに真実である」といえる。
つまり、心理学の理論・法則は一つだけが正しいというわけではなく、それぞれが正しいといえると思う。
また、細山が「一人の人間」として、アドラー、フランクル、フロイト、…のそれぞれの理論を、自分の心の問題に応じて使い分けて使ったり、また精神(心理)療法を応用して自らに使っても、それぞれが役に立ち、矛盾を生じないからである。
アドラー、フランクル、フロイト、……には、それぞれが得手・不得手の領域があり、「深層心理学全体」から見ると、互いに補い合っていて「相補的である」といえる。
物理学に「相補性原理」(ボーア、物質の粒子と波の二面性の原理、1927年)があるが、「心の真理」は両面から、あるいは多面的、多重的(多層的)に見て初めて理解できるようになるのである。
いずれにしても、心の世界、深層心理学にも「心の相補性原理」がなりたっていると思う。
また人間の深層心理、あるいは深層心理学をマンダラ的に見ることができる。
つまり、心の世界、深層心理学全体を密教的な「曼荼羅(マンダラ)」として考えると、その中に「アドラー菩薩」、「フランクル菩薩」、「フロイト菩薩」、……、といろいろな菩薩がいて、活躍した領域が少しずつ異なり、それぞれが心を病む人々を救いながら、人間の深層心理の現象を理論化したといえるのである。
なお、フロイト、アドラー、フランクルの三人に共通していることはユダヤ人であること、いずれも大学専任の精神医学者ではなく開業医や病院の精神科医で、在野の研究者として独創的な研究をしたことなどである。
三人とも大学で教えることもあったが、正統なアカデミズムから見れば、「異端」であった。
このことは、彼らの死後、彼らの説の普及の度合いにも影響をしていて、残念ながら現在にいたっているように思える。
いずれにしても、アドラー、フランクル、フロイトなどの考え方や精神療法などが、現代の日本人がかかえている問題に非常に有効であることには変わりがない。
冒頭にあげたフランクルの伝記が今年、アドラーの伝記が昨年に翻訳されたということは、それぞれの考え方や療法が今後さらに広く理解されて普及することに役立つ。
そして、それぞれが相補的に理解されて普及して、連携プレーができるようになると効果がさらに上がるように思われる。
なお、フランクルをウィーン第三学派と呼んだ研究者がいた。
もちろん、ウィーン第一学派はフロイトの精神分析学、ウィーン第二学派はアドラーの個人心理学のことである。
オーストリアのウィーンには、独創的な研究をしたフロイト、アドラー、フランクルにかぎらず、エリクソンなども住んだことがあり、多くの精神分析家が育ち、第二次世界大戦の前後に世界へ、特にアメリカやイギリスに亡命あるいは移住をしていった。
ウィーンは「精神分析学のメッカ」であるだけではなく、「深層心理学のメッカ」といえる(ユングはスイス)。
『人生があなたを待っている』と『アドラーの生涯』は、いつか機会を見て、ウィーンなどへ行き、彼らが治療した場所や、生活した家などを実際に見ながら、「専門家」のミクロな視点とは異なる「一人の人間(一ライター)」としてのマクロな視点から統合して考えて、彼らの「誤解」を解き、彼らが「和解」をして、さらに多くの日本人、人間に役立つような仕事ができればと、夢を大きくしてくれた。
「ウィーンが細山を待っている」ような気がしている…。
8月8日(火)
例年より遅く、ようやく本格的な夏になったと思ったら、台風7号が上陸するという。
前回の「日記」を書いた後から、あっという間に時間が過ぎてしまった。
「水面下」でいくつかの新しい動きがあったので、その準備をして人に会ったりしていた。
一つは、「サイコー! セラピー」「ご開帳! 聖天さま」などを連載させてくれたマンガ月刊誌「メンズ アクション」(双葉社)が休刊になり(売れ行き不振というわけではなく、諸事情があったようで)、それにともない編集長の秋山敏道さんがマンガの単行本(アクションコミックス)の編集担当になるという人事異動があった。
6月初旬に秋山さんから、描き下ろしのマンガ本企画が何かないかといわれたときに、すぐに『マンガ フランクル』『マンガ アドラー』『マンガ エリクソン』の3冊のことが浮かんだので、企画書をつくりあげて、7月中旬に正式に提案をさせていただいた。
これらは『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』(講談社)をつくっていた7,8年前から実現したいと思っている企画である。
細山の体験では、描き下ろしのマンガ本は一般的に定価が高くては売れず、編集者だけではなく営業、役員など関係者の理解が欠かせない。そして、それぞれの連携プレーがうまくいったときに売れる本が生まれる。
正式な決定はまだであるが、決まって、完成度の高い面白いマンガ本がつくれることを願っている。
『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』の文庫化の件は、6,7月ころにといわれていたが今秋ということになり、その校正ゲラが7月中旬に出たので下旬にかけて見ていた。
同書(原本)は書名や見出しなど、残念ながら納得のできる本ではなかった。
文庫本では、マンガや解説頁の構成、見出し、書名などを変えて、「精神分析・精神医学豆辞典」を巻末につけて、読者の方にわかりやすく買っていただけるに値する面白い本にしていると思う。
今年はフロイト(1856.5.6~1939.9.23)の生誕150年に当たり、世界的にも脳の研究などから「心はエス・自我・超自我」からなるというフロイトの説などが、科学的に裏付けられつつあり見直されている。
岩波書店が『フロイト全集』全22巻、別巻1を今年11月8日から隔月で、4年がかりで刊行する。
この秋に文庫が出版されれば、タイムリーなものになる。
精神分析学をつくったフロイトは、「生物(動物)としての人間の心」を明らかにして、誰にでも通用する「科学的な心理学」をつくろうとしていた。
この110年前のフロイトの夢は、脳を研究する神経科学者などに受け継がれて実現されようとしている。
フロイトは深層心理学のパイオニアであり、神経症などの心の病だけではなく、犯罪・殺人、自殺など、幅広く人間の心と脳の問題を考えることに役立つ。
同文庫は自分の心と人間の心を理解して、楽に生きることにも役立つので、ぜひ多くの人に読んでいただきたいと思っている。
「一家に一冊」いや「一人に一冊」となり、読まれることになって欲しい文庫である。
三つ目は、本「日記」の前回と前々回で広告代理店・大手広告通信社の千崎研司さんの手がけた本について紹介したところ、彼からお礼のメールをいただいた。
そのメールを読みながら、版元さんに合った具体的な企画のアイデアがわき始めて、その後コンセプトなどがまとまったので、千崎さんに8月1日に提案をさせていただいた。
詳細は、ここではまだ書けないが、版元さんに合うように「言葉の力」をキーワード、キーコンセプトにしながら、いろいろなジャンルの人に各巻を執筆していただく企画である。
以上のいずれの企画も、10万部以上売れるように工夫がしてある。
10万部以上売れる本という「こだわり」については、以前に本「日記」に書いたことがあるが、細山が手がけた本で、10万部以上売れた本はまだ2冊しかない。
単独ではないが、『マンガ ユング深層心理学入門』(「細山敏之のプロフィール」を参照)と宮尾登美子『地に伏して花咲く』である。
後者は、単行本が初版15000部で(確か2刷が5000部)、角川文庫に入ったとき初版9万部で、2刷6000部、累計で11万部を超えた。
千崎さんに提案した企画が決まれば、20年以上前に宮尾登美子『地に伏して花咲く』、久保田一竹『命を染めし一竹辻が花』(その後、一竹工房で増刷される。連絡がないので部数はわからないが、神田の古本屋で7刷の本を買ったことがある)をつくった経験と夢(当時、続巻をつくろうとしていたが版元さんが雑誌数誌に失敗して出版社自体がなくなってしまった)や、15年前くらいに雑誌で各界の一流の人に会いインタビューしたことなどが生かせる企画となる。
企画書をつくりながら、当時いつか続巻やインタビューした人の「単行本をつくりたいなー」と思っていたことを思い出した。
ところで、双葉社系の成人マンガを出版しているエンジェル出版の単行本編集のアシストの仕事が7月で終わった(7年7か月になった)。
宮川さん、滝沢さんら4人の若い編集者が送別会をしてくれた。地引さん、秋山さんを呼んでくれて、話ができ楽しい会であった。
お世話になったすべての方々に感謝するとともに、それぞれの方の今後の幅広いご活躍を期待したいと思う。
ここにきて、新しい企画の件を含めて、やりたいことが増えてきてしまっている。
スケジュール、計画を調整し直して、あせらず、あきらめずに一つずつ実現していければと思っている。
人生における新しい段階、ステップに入ってきたようで、「いい響き合い(愛)」があり、「いい出逢い(再会も)」が広がり、「いい連携プレー」ができて、「いい結果がでる」ようになることを念じている…。
6月25日(日)
サッカーのワールドカップ、ドイツ大会で、日本はブラジルに1:4で負けて、予選リーグだけで終わり、決勝リーグへの進出ができなかった。
国際的に活躍をする日本選手が多く出はじめてはいる。しかし、残念ながら日本チームはまだ弱かった。
細山は高校と大学でラグビーを各1年間くらいしていた。当時はサッカーもマイナーなスポーツであったが、今はサッカーが日本ではメジャーな人気のあるスポーツになった。
ぜひ、世界のトップクラスになってほしいものである。
ところで、明治書院から丸山和也弁護士編『臨終デザイン』(四六判、256頁、1365円)が今月10日に発売された。
前回に紹介をした広告代理店・大手広告通信社の千崎研司さんが総合プロデュースなどをされた本である。
サブタイトルとして、「人生の閉じ方、指南します」とあるように、各ジャンルの専門家が、生前の準備(小谷みどり)、相続・遺言状(丸山和也)、葬儀(大竹幸治)、お墓(長江曜子)、自分史(藤田敬治)、辞世の句(坪内稔典)、臓器提供(水谷弘)などについてアドバイスをしてくれている。
自分なりの「人生にケジメのつけ方」の書といえる。
今まで死についてあまり考えたことがなかったり、自分なりの死の迎え方や身内などの死が気になりだした人にはよい本であるので、ぜひお薦めしたい。
まえがきで、編者の丸山弁護士が山本常朝の『葉隠』や新渡戸稲造の『武士道』を引用しながら、死について考えることは生を充実させるためにも有益で、自分なりの死生観をもつことの大切さを書いているが、その通りであると思う。
生と死の問題を考えて死生観をもつ上で、大いなるヒント、手がかりを教えてくれるのが「ホンモノの宗教」である。
細山は死生観についての好きな言葉、考え方がたくさんあるが、自分なりの言葉で結論を書けば、「人間は宇宙の大きな生命(エネルギー)[=空(くう)]の流れの中で奇跡的に生まれてきて、生(い)かされて生き、宇宙の大きな生命(エネルギー)の中に帰(還)っていくのが死である」と思っている。
古代から一部の人間は、この「宇宙の大きな生命(エネルギー)」の流れに気づき、それを象徴的に「神」、あるいは「仏」と表現をして、「宗教」を発展させてきた。
同書に、読者が死生観を考える手がかりを得られる一章があればさらによかったと思うが、一種の「実用書」としてつくっているので、ママでもよいのかもしれない。
別に、読者が死生観を考える手がかりを得られる1冊の本、つまり死ぬことにも生きることにも役立つ本という企画が成り立つので、いつかつくれればと思う。
細山個人としては、現在は同書にあるようなことは、まだ具体的なことは何も考えていない。
まだ「不完全燃焼」であり、「完全燃焼」してから死にたいので、どうしたら「生涯現役」で生き続けて「完全燃焼」できるのかを考えながら、実践中である。
「充実した死」を迎えるために、「充実した生」にしたいと思っている。
「生涯現役」で生き続けて、「完全燃焼」している最中に、知らないうちに死んでいたというのが、理想であるような気がしている。
つまり、自分が生まれたときのことを知らないように、死んでいくことも知らずに生き続けて、この世を去り、宇宙の大きな生命(エネルギー)[=空(くう)]の世界にもどっていくのである…。
ところで、早いもので、本ホームページをつくって丸1年が過ぎてしまった。
思ったことの十分の一、いや百分の一(?)もできていない。
思った以上に書くことに時間がかかることと、いまは書く時間が取れないことによる。
予定は大幅にくるっている。
しかし、急がなくてもよい。ゆっくりでもよいのである。
1か月に1か所の更新でも…(せめて隔週で1回とは思うが)。
そのうちに、集中して時間が取れるようになる。それまでは、我慢、忍耐、……と思っている。
「生涯現役」で生き続けて、「完全燃焼」できるようになるためにも、ホームページは役に立つように思う。
インターネット、ホームページ、ブログ、携帯電話などのデジタル技術・社会・世界の可能性は、無限にある。
人間の意識、深層心理、願望・欲望などのすべてが投影されており、人間の生と死の情報も含まれていて、情報を発信でき、コミュニケーションができるからである。
そのためには、面白くて役に立ち、多くの人に見て、読んでいただけるようにすることが大切であると思っている。
まずは第一ステップとして、原稿を書きためること。
それから次のステップとして、デザイン、レイアウトを変えて、ビジュアル化して、初めて見て、読んでくださる方にも見ごたえ、読みごたえがあるようにしてから、他の関係するサイトに広くリンクをさせていただこうと、現在は思っている。
お互いに「充実した生と死」にするためにも、長い目、あたたかい目で見守ってください。
よろしくお願いいたします。
5月26日(金)
今月初旬に、明治書院から『Dr.金田一&柴田理恵のことば診療所』、宋文洲『コトバノチカラ ビジネスの見方が変わる故事成語』、朝日新聞be編集部編『逆風満帆』の3冊が発売された。
広告代理店・大手広告通信社の千崎研司さんが総合プロデュースなどをされた本である。
明治書院は創業110年になった(る?)国語関係の老舗の出版社である。
いずれも四六判で並製、ソフトカバーの本であるが、専門書としてではなく、読みやすくレイアウトをして写真を入れるなど、ビジュアル的にも楽しめる個性的な一般書に仕上がっている。
定価も、それぞれ1260円、1365円、1050円(税込み)と買いやすく設定をされていてよいと思う。
『Dr.金田一&柴田理恵のことば診療所』のDr.金田一とは、祖父が有名な言語学者の京助、父が春彦という三代目の秀穂(ひでほ)氏である。最近、マスコミにでることが多くなっているようだ。
柴田理恵さんはテレビ、舞台、映画、ラジオなどで活躍する女優である。
人とのコミュニケーションに悩んでいて、「ことば」を上手に使えるようになるための「ことばの診療所」というのが、本書のコンセプトのようである。
人とのコミュニケーションや「言葉遣い」に悩んでいる人には、特にお薦めしたい本である。もちろん、悩んでいなくても、コミュニケーションや「ことば」に関心のある人にも薦めたい。
『コトバノチカラ ビジネスの見方が変わる故事成語』の著者、宋文洲氏は北海道大学大学院に留学したことがあり、日本で土木解析ソフトを開発して事業化にも成功した中国人である。
現在はソフト開発とコンサルティングの会社・ソフトブレーンの会長をしている。
日本人があまり知らない故事成語も入っている。日本人の通常の解釈とは異なっていて、新鮮に感じられて視野が広がる内容になっている。
「ビジネスの見方が変わる」だけではなく、「考え方」「生き方」をも変えてくれるかもしれない…。
『逆風満帆』は朝日新聞の土曜版「be」に掲載された20人のどん底から再起への体験物語である。
高橋尚子、瀬古利彦、岡崎朋美、曙、落合博満、安藤勝己、矢野輝弘、吉原知子、アリー・セリンジャーなどスポーツで活躍している人を中心にしながら、新垣勉,槇原敬之、横山剣などのミュージシャン、作家の山本一力、絲山秋子、映画監督の井筒和幸、華道家の假屋崎省吾、プロ棋士の瀬川昌司、その他、四方修、水谷洋一、辛淑玉の3名である。
それぞれの人が苦難を克服して、成功をした話にはドラマがあり、味わい深くて面白い。いずれも、「心の持ち方」、「考え方」が大切であることも教えてくれる。
深層心理学的にいえば、自分の「アイデンティティ(自我同一性)」を発見して、「自己(自我ではなくSelf)実現」をした人々である。
同書の中で、特に細山の目を引いたのは、バレーボール監督のアリー・セリンジャーである。
彼は1989年から日本の実業団チーム(ダイエー、パイオニア)を指導してVリーグや全日本選手権で優勝をするなど、計10個のタイトルを獲得した。
それまでは「精神論(根性など)」が主流だったが、ブロックの細かい戦略などを導入するとともに、選手の能力や寿命をのばすなどして、日本のバレー界を変えたといわれている。
一昨日の新聞報道によれば、彼はイスラエルに帰るというが、残念なことである。
アリー・セリンジャーは6歳から8歳までユダヤ人強制収容所に入れられた体験をもち、アンネ・フランクと一緒だったことがあるという。
細山が本HPで書いている深層心理学者の5巨人のうち、ユング以外は皆ユダヤ人である。
ユダヤ人はヨーロッパでは差別をされたが、逆境を乗りこえている。
彼らはユダヤ人であることを誇りにしながらも、とらわれすぎずに、物理学者のアインシュタインを含めて、「世界的で人類に普遍的な仕事」をしている尊敬すべき人たちである。
細山は日本人が学ぶに値する民族であると思っている。
ところで、千崎さんとの出会いは細山が『マンガ ユング深層心理学入門』をつくっていたときに、TBSのプロデューサーだった大山勝美氏などがつくった「メディア・ワークショップ」のディレクター・コースで知り合った。
大学の卒論でユングを書いたとのことなどで、不思議な因縁(!?)と親しみを感じた。もう20年(!?)前になってしまう…。
細山が丸善で10冊の科学コミックスをつくったときには、『マンガ ニュートン』『マンガ アインシュタイン』のシナリオを犬上博史のペンネームで書いていただいた。
昨年、千崎さんが明治書院の企画を手がけ始めたときに、ジャンルは問わずに数万部は売れる本の企画を求められたので提案をしたが、その後、国語、言葉に関係のある企画ということなど(理由は他にもあるようだが…)でペンディングになった。
明治書院さんの企画にこだわらずに、千崎さんには小生が考えている新雑誌の企画でも協力をしていただいて、また一緒に仕事ができればと思っている。
なお、明治書院では今後も国語、言葉などに関係する本で数万部は売れる本であれば出版されるようなので、よい企画があれば、ご提案をしていただきたい。
それと、遅くなってしまったが、地引功一さんが双葉社に勤めていたときに紹介された井上宏生さんが書かれた『神さまと神社』(祥伝社新書、3月5日発行)も合わせて紹介したい。
3月末に井上さんの飲み会があり、そのときには重版になったという話を聞いた。
サブタイトルに「日本人なら知っておきたい八百万(やおろず)の世界」とあるように、神話なども含めてわかりやすく解説した「神道の入門書」になっている。
ユングなどが研究をしたように、神話と深層心理には関係がある。当然、日本の神話は日本人の深層心理に関係をしている。これについては、機会をみて書きたいと思っている。
新刊書のことで、まだ書きたいこともあるが、今回はとりあえず、ここまでにしたい。
3月21日(火)
「2006年ワールド ベースボール クラシック」決勝で、日本(王ジャパン)がキューバに10対6で勝ち、初代の世界チャンピョンになりました。
日本人が世界一になるということは、嬉しいことです。日本人が世界に通用することを証明してくれるからです。
それを祝うかのように、東京の桜は今日、開花したようです。
さて、禅寺(曹洞宗)、東川院(とうせんいん)の住職である藤野悦道さんが、3月17日にホームページを立ち上げられました。
バラエティーにとみ充実した内容になっています。
ご自身の「心のコペルニクス的転回」(「心の天動説」から「心の地動説」へ。本「日記」2月1日参照)の体験についても書かれていて、ためになります。
本HP、「ナビ10」でリンクさせていただきましたので、ぜひご覧ください。
一般的に、お寺の坊さんは葬式などの法事や観光などの仕事だけをしているものと思っている人が多いようです。
それも事実かもしれませんが、伝統仏教の各宗派には人数は多くはないと思いますが、本格的に修行をして、道を究めようとしている人たちがいます。
しかし、そうしたお坊さんとわれわれ一般人との接点は、残念ながらほとんどありません。あったとしても、多くの人々には、会う縁や機会がなかなかありません。
お寺に生まれて世襲で坊さんになり住職になるのは、そう難しくありません。しかし、藤野さんのように在家出身で修行をして、禅寺の住職になるのは、やさしいことではないと思います。
そうした禅僧、仏教者の人が「デジタル社会(世界)」にも情報を発信されることは、深層心理学的にも大変に意義があることだと思います。
なお、曹洞宗の総本山、永平寺の宮崎奕保貫首は今年105歳(明治34年生まれ)になられる(た?)ようですが、一般的にお坊さんは長命で、50代60代の住職さんはまだまだ「若手」であるようです。
藤野さんのますますのご活躍を期待したいと思っています。
同時に、一般の在家の人間であるわれわれも、少しでも見習わせていただき、生きたいと思っています。
ところで、また「だいわ文庫」(大和書房)のことです。
前回(3/1)書いた後、3月5日には、『ユダヤ人大富豪の教え』(本田健)が15万部突破(3/15、18万部)、『愛がなくてははじまらない。』(唯川恵)が12万部、『35歳からの美肌カウンセリング』(佐伯チズ)が10万部という広告がでていました。
発売後、1か月以内に、すでに3点が10万部を超えたわけで、スゴイことです!
「5,6点は10万部をいくのかもしれない」と予想をしましたが、7,8点はいくのかもしれません。
3月10日には、創刊第2弾として、『若きいのちの日記 「愛と死をみつめて」の記録』(大島みち子)、『グズをなおせば人生はうまくいく』(斉藤茂太)、『ついつい!「あいまい」に使っちゃう日本語の本』(日本社)、『最強トヨタの7つの習慣』(若松義人)、『黒幕 昭和闇の支配者 一巻』(大下英治)、『落語CD&DVD名盤案内』(矢野誠一・草柳俊一)、『ひみつブック』(おーなり由子)、『サン=テグジュぺリ 星の言葉』(齋藤孝 選・訳) の8点が発売されました。
多ジャンルにわたり、日本の出版社の文庫では一番幅の広いものになるのかもしれません。
編集長の古屋さんはすでに、本の背や帯にジャンルわけのアルファベット記号を入れられていて、読者にわかりやすく、本が売れやすいように工夫をして仕掛けられています。
3月15日に朝日新聞で1ページ全面のカラー広告を見て、「大胆で、すごいナー」と感じました。
なぜなら、広告は読者に対してだけではなく、取次ぎや書店さんに編集者や出版社の「意気込み、やる気」を伝え影響を与えて、書店における平台や棚の確保につながり、本を売ることの布石になるからです。
最近、幻冬舎などが新聞の全5段で1冊の本を広告するという方法をひんぱんに使い、大胆だなーと感じていましたが、それに勝るとも劣らぬ、いや勝る大胆な広告の打ち方だと感じました。
今後、どれだけ売れていくのかを楽しみにしています。
なお、 『愛と死を見つめて』(大島みち子・河野実)のテレビ朝日のドラマ(3/18・19)をみました。
人生の残酷さ、悲しさ、愛、勇気などに、涙なくしては見られませんでした。
昨年11月3日の本HPの「日記」に書いたときには、同書が大和書房から出版されていたことは知っていましたが、「だいわ文庫」に入るとは知りませんでした。古屋さんからの年賀状で知りました。
大島みち子さん(ミコ)が顔面の下にできた軟骨肉腫という不治の病に向かいあい、立ち向かって生きる勇気をもちながら、なぜ他の人々に優しくできたのかを早く知りたくて、『愛と死を見つめて』『若きいのちの日記』を拾い読みしてみました。
ミコは心のよりどころとしてキリスト教などに関心をもちましたが、信仰するにはいたらなかったようです。
彼女が絶望して自殺を考えていたときに、手術を受けて生きることを決心させたのはマコでした。
ミコは、またマコは「お互いを信じる」ことができたのです。
外界の神仏を信じなくても、すでに神仏が二人の心の中に現われていたといえます!
「響きあい(愛)に命」があったのです!!
お互いが信じあえてトラウマを治せた最高のカップルであったといえます(ナビ7「男と女の関係の10段階説」、第8段階)。
ミコは担当医に紹介をされて、医療社会事業(メディカル・ソーシャル・ワーカー)の先生に会い、元気になれたら、その仕事をしたいという希望、夢をもち、すぐに病院の中で他の入院患者のために奉仕活動を実践し始めたようです。
そのことは、彼女の心に大きなよい影響を与えたようです。
ミコは死という不安と闘いながら、マコや両親、兄妹、医師など多くの人々の愛情に支えられながらも、自らの意思と努力で、「心のコペルニクス的転回」をしていったように思います。
ミコが短命であったことは、不幸なことであったかもしれませんが、多くの人々に生きる勇気、生命、愛の尊さを教えてくれた「菩薩(ぼさつ)」であったと、改めて思いました。
上記の文庫本は、愛と死、人生などについて考えさせてくれて、「心の持ち方」の大切さを教えてくれる本ですので、ぜひお薦めします。
細山にとっては、「心と愛(慈悲、アガペー)」(Psychology & Love)の大切さを再確認させてくれて、さらに取り組むようにと励ましてくれるドラマと文庫本になりました…。
3月1日(水)
禅寺の住職である藤野さんと東京で、先日またお会いしました(本「日記」、昨年8月1日参照)。
ホームページを作成中で、今月中には立ち上げられるとのことで楽しみにしています。
内容は豊富で、坐禅や仏教のことを、ご自分の体験をもとに、やさしい日常の言葉で書きたいとのことでしたので、社会的に意義があり大変によいことだと思いました。
立ち上げ次第メールをいただけることになり、相互にリンクをしあうことになりましたので、ぜひご覧ください。
「よろず悩みごと相談」のページも設けられるとのことですので、相談をしたい方はぜひしてください。
相談ではなく質問をされても、わかりやすく教えてもらえると思います。
「禅問答」(?)を体験されると、「心のコペルニクス的転回」(本「日記」、2月1日参照)に役立つと思いますので…。
「細山くんの日記ページは、『月記』か『旬記』で『日記』ではない」といわれてしまいましたが、ごもっともです。
日記にしたいという願望はあるのですが、「時どき帳」あるいは「思いつき帳」とか、何かよいネーミングに変えてもよいかなと思い始めました。
いまは目先のことを、いろいろとこなさないといけないので、それぞれのページの更新をする時間が残念ながらとれません。早く更新ができる日がくることを「夢」見ながら、あせらず、あわてずにこなしていきたいと思ってます。
話はかわりますが、本職の件でお世話になっている大和書房の古屋さんが、「だいわ文庫」を2月8日に創刊されました。
『愛と死を見つめて』大島みち子・河野実、『対話する生と死』河合隼雄、『マンガ仏教入門』作画・蔡志忠、監修・玄侑宗久、訳・瀬川千秋、『天才の読み方』斉藤孝、『ユダヤ人大富豪の教え』本田健、『愛がなくてははじまらない。』唯川恵、『35歳からの美肌カウンセリング』佐伯チズ、『JAZZピアノ・トリオ名盤500』寺島靖国、『秘史「乗っ取り屋」』有森隆+グループK、『これで世の中わかる! ニュースの基礎の基礎』池上彰、の10点です。
初版は2,3万部から6万部くらいとのことでしたが、2週間後には『ユダヤ人大富豪の教え』が15万部突破、最後からの3冊が重版という新聞広告(半5)を出されていましたので、立ち上げに成功をされたといえるかと思います。
「さすが!」だと思いました。
昨年、お会いしたときには、2、3点は10万部はいくと思うと謙虚におっしゃっていましたが、5,6点はいくのかもしれません。
なお、3月は8冊発行をし、その後は毎月5冊前後になる予定のようです。
古屋さんは昨年5月に講談社を定年になり、8月から大和書房の仕事を始められました。
講談社にいたときには、鈴木健二『気くばりのすすめ』(430万部)、浜田幸一『日本をダメにした九人の政治家』(175万部)などの大ベストセラーになる本を編集されたり、講談社+α文庫(『つい誰かに話したくなる雑学の本』は160万部?など)、+α新書などを立ち上げられるなどのご実績があり、出版業界でも有名な方です。
古屋さんのノウハウや考え方、姿勢などを学ばせていただき、少しでも実行できるようになれればと思っています。
読者に買っていただける本、読んでいただける本とするために、よく工夫をされています。
たとえば書名のネーミングや装丁などのディレクションの巧さはもちろん、社会や時代の流れ、人々のニーズなどのポイントを見抜き、発想が広く、「切り口」が大胆で、細かいところもするべきことはして、巻末の広告まで適確に入れたり、センスのよさ、バランス感覚など、いろいろと感じさせられます。
いずれにしても、「本ホームページを充実させる」という夢を実現できる余裕をもてるようにするためにも、当面は「10万部を超える本を書いたり、つくる」という夢、目標をもちながら、目先のことをこなしていこうと思っています…。
最近、「10万部を超える雑誌をつくりたい」という夢ももち始めてしまいました(企画書の第1案はできています)。これも実現できればと思っていますが……。
ご協力をよろしくお願いいたします。
2月1日(水)
ライブドア問題や耐震構造疑装問題など、「金(かね)至上主義」的な発想で仕事をしたり生きる人が、だいぶ多くなってきたようです。
以前、TVコマーシャルで子どもが「お金は大事だよー」というのがあったが、ほんとうに大切であると痛切に思う。
しかし、「金至上主義」が個人的な主義、主張で個人の生活段階である場合などにはよいが、会社ぐるみで犯罪的な行為をして、多くの被害者が出ると、やはり大きな問題である。
彼らに共通していることは、目先の自分の欲望、金に執着をしすぎていることであるが、深層心理学的な視点から見た場合には、完全な「自己中心主義者」になってしまっているといえる。
おととし、お金に対する考え方で、「すごいなー! なるほど!!」と思った言葉に出会った。
それは、「君子は財を愛し、これを取るに道をもってす」である。
西村恵信著『私の十牛図』(法蔵館)にでてきたので、よけいに印象的であったのだと思う。
なぜなら、著者は臨済宗の禅僧で、現在は花園大学の学長であるが、禅の場合には、あらゆる欲望やお金に対するこだわりを解き払って、「真の自己」を探求するものと思っていたからである。
この言葉は、京都・南禅寺の台所にある、托鉢(たくはつ)で得た浄財を入れる箱のフタに書かれているという。
余談ではあるが、細山は15年くらい前に、著者が花園大学の教授であったときに京都と東京でお会いした。ある出版社のPR誌で曹洞宗の駒澤大学の桜井秀雄先生と対談していただくことを依頼して、対談をしていただいたからである。
「道」とは「道理」のことで、簡単に言ってしまえば、「道理にかなった方法で、人々のため、社会のためになることをして、財つまりお金を稼ぐ」ということであろう。
これができて、初めて「プロ中のプロの仕事」といえるのかもしれない…。
人間はなかなか「人のため、社会のために」という発想が出てきそうで出てこない。あるいは、言葉や頭ではわかっていても、なかなか実践することができない。
本来、生物としての人間は、「自己中心主義者」になりやすいようにできているからである。
しかし、社会の中で生きている人間は、「自己中心主義者」のままでは、いきづまることを体験する。
ところで、フロイトやアドラー、ユング、エリクソン、フランクルなどの深層心理学者の理論を統合して考えると、彼らは「自分のためだけに生きるのではなく、社会の中で人々のために生きられるような自分になること」が、心を病まずに自分を生かして生きるために、もっとも大切なことであることを明らかにしている。
フロイトは「自我が心の中心ではなく、無意識が中心」と考えたとき、自らの深層心理学的な意味と価値を、科学史におけるコペルニクスと同様に、人類史において重要な発見をしたことを自覚していた。
また、フランクルは「精神的無意識、無意識の神」が心の中にあることをとなえて(本ホームページ、ナビ1、05.6.21)、「心のコペルニクス的転回」の大切さを主張した。
ちなみに、コペルニクス(1473~1543)は理論的に、「天動説」(地球を中心にして太陽などが回っている)ではなく、「地動説」(太陽を中心にして地球が回っている)をとなえた。
木星の衛星や金星の満ち欠けなどの天体の観測から「地動説」を実証して主張したのが、ガリレオ(1564~1642)である。彼は宗教裁判にかけられて有罪になったが、「それでも地球は動く」といったエピソードは有名である。
「自己中心主義者」にかぎらず、ふつう人間は「心の天動説」、つまり自分を中心にして物事が動いていると考えて生きているのではないだろうか……。
先ほどの「君子は財を愛し、これを取るに道をもってす」は、「心の地動説」つまり社会・人々などの回りを自分が動いて、心を使い生きることの大切さを言っているように思われる。
この言葉の深層には、仏教の「慈悲」、キリスト教の「愛(アガペー)」の考えがあると思われる。
最近、深層心理学において「コペルニクス的な結論」にあたるものが、禅を含む仏教、キリスト教などの「ホンモノの宗教の結論」と一致しているように思い始めている。
それを自らの体験や症例から証明しているのが、フロイトやアドラー、ユング、エリクソン、フランクルなどの深層心理学者たちであるように思われる。つまり、「ガリレオたち」である。
「心のコペルニクス的転回」ができて、「自分のために生きるのではなく、社会、人々のために生きることができれば、心を病まずに、よい人生にすることができる」というのが、「ホンモノの宗教」と深層心理学の結論のようである。
この詳細は、本HPの「ナビ1」などや、執筆している本で書きたいと思っている。
もちろん、書くだけではなく、自分の人生において、実践、実現することが、大きな課題ではあるが…。
現在、日本人の多くが「個人主義者」になってきているという構造的な問題も気になっているが、冒頭のライブドア問題や耐震構造疑装問題を起こした人のなかから、「心のコペルニクス的転回」をした人間が出てきて欲しいと思っている。
もちろん、その可能性は残念ながら少ないのかもしれない……。
しかし、よい言葉や考え方、よい人との出逢いがあり、「心のコペルニクス的転回」をして、彼らが再起、再生することを心から祈りたいと思う。
1月3日(火)
あけまして、おめでとうございます。
今年は、昨年から手がけてきた単行本関係を早く仕上げることと、新しい企画の準備をすること、それと雑誌も手がけられたらいいなと思っています。 いずれも深層心理学などや本HPに関連することが中心になります。
もちろん、本ホームページのナビ1、2、7などを、できるだけ早く更新したいとは思っていますが、目先のことを早くこなす必要があるため、更新は残念ながら、ゆっくりしたペースになるかもしれません…。
いずれにしても、心の問題は結局、根底に愛情の不足・ゆがみの問題があるようなので、日本が「愛(慈悲)のある社会」になることに、大きく貢献できたらいいなという秘かな(おおいなる!?)夢を実現したいと思っています。
なお、元旦の新聞広告で一つ驚いたことがあります。
それは、岩波書店が今年10月からフロイト全集(全22巻、別巻1)を刊行することです。
いままで日本では、フロイトの全集は日本教文社や人文書院から出版されました(それぞれ約35年、30年前に完結していますが)。まさか全集がまた出版されるとは、思ってもいませんでした。
以前、この日記に、フロイトの名前を知らない若い編集者の話や、彼の説を知らない精神科医や臨床心理士、カウンセラーの活躍がマスコミでも目立つことを書きました(専門が違うといえば、それまでですが…)。
フロイトの精神分析学は科学的な根拠がないという批判がずっとありましたが(その批判の本を読んで批判をしている人も目立ちます)、欧米では脳の研究をする神経科学者や精神分析家が2000年に国際神経精神分析学会をつくり、フロイトの説を科学的に実証しつつあることも、本HPに書きましたが、フロイトを見直す国際的な動きをとらえたのかもしれません。
また、確か彼の死後50年か100年(年数は不正確ですが、彼は1939年に死去)は公開してはいけないというフロイトの日記や往復書簡などが公開されたはずで、これらも入るのかもしれません。
精神分析系以外の心理学や精神科医の先生方にも幅広く、フロイトと彼の理論などを研究していただき、一般の人々が生活に、生きることに早く役立つようになればいいなと思います。
フロイトの精神分析学の理論は、心と現実とのかかわりを考えるときに非常に有効なので、普及の必要性を感じていた細山としては、非常に喜んでいます。「追い風」が吹いてくるのかもしれないと感じています。
本年も、よろしくお願いいたします。
トップページに戻る
2005年(平成17年)
12月29日(木)
時間が過ぎるのは本当に早いものです。今年も、あと2日になりました。
本HPに書きたいことは、いくつもあったのですが、前回の日記を書いた後、仕事のことで二つのことがあってできませんでした。
一つは、ある人から単行本の企画を提案して欲しいと言われていたので、現在書いている本と連動する深層心理学の入門書で、読者に読みやすく買ってもらいやすい(売れる)アイデアが浮かんだので、企画書をつくり、先月末に提案しました。版元さんが専門出版社なので、企画が合うかどうかなど、いくつかの課題がありますが…。
もう一つは、今月13日にマンガ雑誌の編集長Aさんと飲んでいたら、何でもいいから雑誌企画を提案して欲しいという話が出て、その前日に買ったポプラ社の一般向けの心理学雑誌「月刊psiko(プシコ)」が浮かび、話しながら同誌とは異なった切り口のコンセプトが一気に湧いてきましたので、企画書にまとめて21日に提案しました。
ある意味で、「大胆で面白い企画」なのですが、まだここに書けないのが残念です。
「月刊psiko(プシコ)」は今月7日に創刊号が出たのですが、10日に新聞数紙に全5段の大きな広告を出したようで、「力(リキ)が入っているナー」と感じました。それと、ポプラ社さんは確か児童書を中心とする出版社なので意外でした。
今まで心理学の専門雑誌はありましたが、一般誌はありませんでしたので、広告を見たときに、「ついに出たかー、そうだよなー、あってもいいよなー、必要な時代、日本社会だよなー」などと思いました。
というのは、ある程度、心理学を広く知ると、殺人や性犯罪者の再犯問題、自殺、さまざまな心の病、ニート、離婚など男女の問題にしても、専門家の考え方や理論、治療法など、解決策はたくさんあるのですが、それが一般の人々、マスコミ、行政、政治家にあまり伝わらず、社会の遅れが目立つからです。
専門家と非専門家の間のギャップが非常にあるのです。
また、「専門家の専門化」が進み、心理学の全体や複数のジャンルがわかる心理学者や精神科医などが少なくて(いなくて?)、各専門を組み合わせて「個々のジャンルの力」や「心理学・精神医学全体の力」が現実に十分に発揮されずに、「心理学・精神医学の知的財産」が「個々の部屋や書庫の中に眠ってしまっている」という状況にもあります。
このことを感じたので、細山は本ホームページをつくり始めました。
事件を起こしたり、症状が出たら専門家に治してもらうというのでは遅いともいえます。専門家の成果や「知恵」を自分で取り入れて、生活して生きていくことが大切になってきています。また、心理学・精神医学の成果や「知恵」を利用できる社会体制や教育、雑誌ができれば、多くの人々が救われて、よい人生にすることができるのです。
「月刊psiko(プシコ)」ですべての問題が扱えたり解決するというわけではなく、健康雑誌や男性誌、女性誌などさまざまなジャンルの雑誌が複数あるように、今後数誌が創刊されてもよいように思います。
それは競合することではなく、棲み分けができて共存共栄して、マーケットが広がると思います。
企画を提案した翌日、ポプラ社の社長に取材をした記事がある新聞に出ていましたが、好調な売れ行きとのことです。
同誌は現編集長が一人でつくって会員制で販売をしていたのですが、資金難から行き詰まって、ポプラ社の社長に話が持ち込まれて、坂井社長は2分で即決したといいます。
すばらしい話です! まさに「響き合い(愛)に命あり」(細山の造語)でしょうか!!
なお、11月23日に大学の研究室の同窓会、11月25日に双葉社を定年になった女性編集者を送る会があり、書きたいと思っていたのですが、その女性編集者がつくった本に『性同一性障害30人のカミングアウト』(監修・針間克己、編著・相馬佐江子、2004年7月、1600円)という本があることを記すにとどめます(なぜ性同一性障害になるのかは、まだわからないようです)。
それと、入居しているマンションに先月、光ファイバーがひかれたので申し込み、今月初旬に工事をしてもらいました。料金はADSLのときより安くなり、携帯電話より安く使える時代になったのですから、凄い時代になったと思います。
このことは来年、機会を見て書いてみたいと思っています。
お読みいただき有難うございました。
よいお年をお迎えください。
来年も、よろしくお願いいたします。
11月15日(火)
母親に劇薬のタリウムを飲ませて殺そうとして、静岡県の県立高校一年の女子生徒が逮捕されたり、東京都町田市の都立高校一年の男子生徒が女子生徒を殺して逮捕されたりと、痛ましい悲惨な事件が立て続けに起こっています。
こうした事件は、今後も起こってしまうものと思われます。いや、残念ながら増えるのかもしれません。
いずれも、フロイトのいう攻撃的な「死の本能」が活発になり、身近な他者に向かって行動してしまい起きた事件といえます。
また、「エス・自我・超自我」のうちの「超自我」が働かずに、「無意識のエス」が「自我」に行動をさせてしまった事件・現象ともいえます。
『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』の監修者は福島章 上智大学名誉教授ですが、先生は精神分析学を犯罪心理学に応用して、多くの犯罪者の精神鑑定や精神分析をしています。
上記2つの事件の具体的な原因の詳細はまだわかりませんが、福島章先生の『非行心理学入門』『犯罪心理学入門』『愛の幻想』『犯罪精神医学入門』(いずれも中公新書)、『殺人と犯罪の深層心理』(講談社+α文庫)などを読むと、少年に限らず大人の殺人事件も、なぜ起こるのかがよくわかります。
これらの本では、マスコミがいう少年の「心の闇」が解明されています。
少年犯罪が起こると、テレビで先生が事件のコメントをされていることが多くあります。
時間の制約や事件が未解決である段階であるためか歯切れが悪い場合が多いのですが、なぜこうした事件が起こるのかを、もっとフロイトの精神分析学の原理的なことをコメントされたほうが、視聴者には有益なのではといつも感じています。
最近は、心理的な問題だけではなく、脳の発達に先天的に異変がある広汎性発達障害、アスペルガー障害が注目されているようです(緊急対談、十一元三vs.草薙厚子「少年犯罪と脳」[「週刊現代」2005.11.26号])。
原因が心理的な問題だけではなく脳であればこそ、高校生や中学生くらいから、本ホームページが提案している「古典深層心理学」を学校や家庭で学べるように早くすることが、犯罪の防止にも役立つように思います。
フロイトの精神分析学は「人間としての自分の心」を理解することに欠かせません。
上記のような問題の解決にすぐに役立つのは、非行少年や犯罪者には「共同体感覚」(社会に貢献しようという意識)が欠如していることを端的に指摘したアドラーや、アメリカの刑務所で講演をして囚人を改心させたフランクルの考え方です。
長期的な真の更正には、エリクソンやユングの考え方などが役立つと思います。
先日、NHKのTVで、再犯をしてしまう性犯罪者の日本の刑務所内における更正教育の取り組みが放送されていましたが、担当者の発言を聞いていると、暗中模索をしているようで、「深層心理学」的な視点がほとんど欠如しているように思いました。
いずれにしても、本ホームページなどが少しでも(本心は、大いに!! 多いに!?)役立てばと思っています…。
11月3日(木)
前回の日記(10/17)や、ナビ3「深層心理学の5巨人について」の第4回「よみがえるフロイトの夢」(10/27)に書いたこと、あるいは本HP全体に関係することを、TV番組を見ていて思いつきました。
それは、10/29(土)、午後7時30分~8時45分のNHKTV「土曜特集~昭和人物伝・ペルソナα」の中で紹介されていた「大島みち子“愛と死を見つめて”」のことです。
彼女は昭和16年生まれで、同志社大学の学生だったとき、軟骨肉腫になり手術をしましたが治らず、昭和37年に21歳で亡くなりました。
彼女(ミコ)と恋人の河野実(マコ)氏の往復書簡集『愛と死を見つめて』は、大ベストセラー(135万部)になりました。
残念ながら、細山はこの本をまだ読んでいません。ですが、大ベストセラーになり、日活で映画化されたこと(吉永小百合と浜田光夫)や、確か青山和子の歌も大ヒットしたという記憶があります。
まず、『愛と死を見つめて』という書名に、ドキッとしました。
なぜなら、フロイトの言葉でいえば、『エロスとタナトスを見つめて』ということになるからです。
この二つのことを見つめて、二人の出逢い、実際に起こった出来事、感情、気持ちを表現して、人々に感動を与えたのが同書だと思います。
番組の中でいわれていましたが、彼女は手術後、自らのことより、入院している他の恵まれない患者さんの世話をして尽くしたということです。
第2番目のことは、フランクルのいう創造的価値、体験的価値、態度的価値の3つの価値のうちの「態度的価値」を、彼女が実現したことです。
「態度的価値」とは、逃れられない死や病気などになったときに、それを受け入れて、生きる態度によって価値を実現することです(ナビ1で、次回かその次に書こうとしています)。
第3,4番目のことは、彼女はアドラーのいう「社会・同胞に尽くす」という「共同体感覚」をもち、そう行動することが自分の「アイデンティティ(自我同一性)」だと思っていたようです。
「アイデンティティ」とはエリクソンの言葉で、自分の社会的な役割や生きがいを自覚することです(いずれも、ナビ1で書きます)。
第5番目のことは、番組名の一部の「ペルソナα」ですが、ペルソナという言葉はユングが重視した言葉で、社会的な外界に対する自分の「仮面」のことで、職業や身分、社会的な立場などのことをいいます。
「ペルソナα」はペルソナだけではなく、+アルファをした、つまり「自己実現をした人」という意味があると思いました。
なお、ユングのいう「自己実現」の自己は「自己中心主義、利己主義」などというときの狭い「自己」ではありません。
人類に普遍的な集合的な無意識(自他の区別がなくなった深層心理、自他が同じ生命であるという無意識)にもとづいた「自己(Self)」(小文字のselfではなく大文字)であります(その詳細は、ナビ1でユングを取り上げたときに説明をします)。
これは余談かもしれませんが、ある有名な大学の助教授の先生(臨床心理士)が、「トランスパーソナル心理学」についての本の中で、「この成熟した社会の中で生まれてくる問題は、もう、自己実現をスローガンとする心理学では解決できません」「自己実現というスローガンは既にその役割を果たし終えています」(45頁)と堂々と書いているのを読んで驚いたことがあります。
これは、まったく逆です!!
多くの若者が「自己実現」する道、方法がまったくわからないから、人をいじめたり、引きこもったり、ニートやフリーターになっているわけです。
また大人でも、うつ病になり自殺をしたり、暴力を振るい殺人をしたりするわけで、あらゆる人々が「自己実現」できるようになれば、あらゆる人々の心の病は治るわけです!
その手助けをするのが、臨床心理士の社会的な使命だと思うのですが……。
その先生は同頁では、ユングの名前を書いていないのですが、他の頁(79頁)でユングを批判しています。
「自己実現」を「自分の欲望・願望を実現する利己主義」と勘違い(?)をされているようでした。
要は、ユングをちゃんと理解せずに、批判をしてしまっているのです!
本当は、ズバリを実名、書名を出して批判をするのがよいのかもしれませんが、ご本人の名誉を傷つけてもいけませんし、自分も似たような誤りをするかもしれませんので控えます。ただし、その本(一流の出版社からでている新書)を勉強のために読みたいという方がいらっしゃいましたら、メールをくださればお教えいたします。
ユングのいう「自己」とは、まさにトランスパーソナル(自己[personal→persona・ペルソナ]超越)した自己[Self]、つまり「自分・自己[personal→persona]を超越した自己[Self]」なのですが、そのことをまったくご理解されていないようです。
専門家としてはお粗末な話なのですが、一歩、心理学の世界をのぞくと、実にジャンルが多岐にわたることがわかり、とても一人ではカバーしきれません。
トランスパーソナル心理学でもいろいろな人が活躍していますから、メインの人を理解されることだけで手一杯で、ユングまでは学びきれていないのだとは思いますが……。
専門家の先生の本を読んでいると、自分で批判する相手を誤解して、あるいは真意を理解せずに、誤ったレッテルを貼っておいて、それで相手を批判しているということが目立ちます。
本HPでは、そうした誤解を解くためにも、5巨人を平等に扱い、長所について伝えようとしているのです。
さて、本論にもどると、大島みち子さんが短命であったことは非常に残念でしたが、でも真の意味で「自己実現」をした、できたのが彼女であると思います。
彼女の生き方、死に対する態度は、「深層心理学の5巨人」も高く評価するでしょう。
彼女は5巨人のことを知らなかったかもしれませんが、彼女は5巨人の考え方を統合して生きて死んでいったといえます。
細山流の仏教的な言い方をさせていただくと、「大島みち子さんは菩薩として現われて、去っていった…」のです。
『愛と死を見つめて』の本については、もう一つ書きたいことがあるのですが、それは来年になってから書きたいと思います。
10月17日(月)
ごぶさたしています。時間がたつのは、本当に早いですね。
本HPを更新したいと思いながらも、ここだけの話なのですが(まだ他の人に言わないでくださいね)、ある出版社から 『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』(現在、品切れ)が文庫化されることになり、読み返して赤字を入れて、欄外の注を補足したり、巻末の「読書案内」に最近の本などを補っていました。
頭の中では簡単にできると思っていたことが、いざしてみると、時間がかかってしまいます。
編集の打ち合わせをしていたときに、最近はフロイトの名前を知らない若い編集者がいると聞き驚きました!
ということは、「フロイト」の「知名度」も低くなっていて、読者をひきつけなく売れなくなっていることを意味します。
フロイトの「精神分析学」は、彼の『精神分析入門』などを読んでも、残念ながら1冊読んだだけでは多分わからないと思います。
専門家にはよいのかもしれませんが(?)、素直に言ってしまえば、素人には記述が詳細すぎて、「冗舌(じょうぜつ)」に感じて、眠くなってしまう(?)でしょう。彼はゲーテ賞を受賞するなど、名文家といわれましたが……。
彼の「精神分析学」は、心を病んでいなくても、自分や人間の心を知り、生きていく上で非常に有益です。
しかし、一般の人々が手短に知ることができる本がなかなかありません。
その点、 『マンガ フロイト』は便利でよい本であると思っています(自画自賛ならぬ、自我自賛!?)。
また、本HPの試みや、「古典(普遍的)深層心理学」を提案したり、本を書こうとしているのも、手短に「精神分析学」の長所を多くの人に知っていただければと思っているからでもあります。
フロイトの精神分析学は、過去の古いものだと考えている専門家も多いように思われますが、 最近、フロイトの説のうちの2つのことが、科学的に裏づけられています。
その一つは、フロイトの「心はエス・自我・超自我からなる」という説です。
脳の研究が進み「脳地図」が明らかになり、それぞれの領域がほぼわかったようです。
エスとはドイツ語で、英語のit、「それ」の意味で、性や生の欲動と、攻撃的な欲動の生じる「無意識」の領域です。脳幹や辺縁系の領域が相当しているようです。なお、英訳されたときに、ラテン語のイド(ido)が使われました。
自我は意識している領域で、後部皮質です。
超自我は文化や伝統的な考え方で自我を抑制したり制御する役割があり、背側・腹側前頭皮質の領域が相当しています。
この「エス・自我・超自我」の調和がとれれば、よい生き方ができるわけですが、殺人や犯罪、自殺、神経症、精神病などの心の病にかかる人は、「エス・自我・超自我」のバランスが崩れてしまっているといえます。
もう一つ、細山が注目していることは、「人間はエロス(性を含む生の本能)とタナトス(破壊・攻撃を含む死の本能)の二つの本能をもつ」というフロイトの説のうちの「タナトス」のことです。
遺伝子の研究が進み、細胞死の現象(アポトーシス)が遺伝子によって起こっていることが明らかになり、そのメカニズムを明らかにした3人の研究者が、2002年度のノーベル賞を受賞しました。
フロイトの「タナトス(死の本能)」は観念的で客観的な裏づけがない、ペシミスティックであるということで、認めたがらない精神分析家が多かったようです。もちろんキリスト教文化圏の多くの人々も認めませんでした。
肉体の(自)死のメカニズムが明らかになったわけですから、フロイトの直観力、洞察力の鋭さには驚かされます。
細胞死の現象(アポトーシス)の研究は、ガンやエイズ、アルツハイマー病など不治の病の新しい治療法に役立つようです。
肉体と心には相互関係があるわけですから、フロイトの「タナトス(死の本能)」について研究を進めることは、重い心の病を治すことに有益になるかもしれません。
この2つのことは機会を見て、「ナビ3」にまた書きたいと思っています。
神経科医であったフロイトは、早い時期から「人類に普遍的で科学的な心理学」、つまり「誰にでも通用する心理学」をつくりたいという夢をもっていました。
100年くらい前の「フロイトの夢」がかないつつあるのですから、すごいことで、素晴らしいことです。
先ほどの若い編集者の人に限らず、マスコミで活躍している若手(中堅?)の精神科医や精神医学者、臨床心理士、カウンセラーの人の発言を聞いたり、書いたものを読んでいても、「この人はフロイトのことを知らないで話をしたり、書いているな」という人が目立ちます。
そのためには、上記の4つのことを考慮して、今後「フロイトの精神分析学」を見直して研究する専門家の出現が望まれます。
そうした意味では、上記の4つのことを考慮して、『マンガ フロイト』を再編集して文庫化することは、非常に現代的な意味と価値があると思っています。
編集責任者の方(まだ実名を書けないのが残念です)から、大胆でよいアドバイス、ディレクションをいただきましたので、検討をして準備作業をしています。
多くの読者の方々に喜んで買っていただき、読んでいただけるように、面白い本に再編集したいと思って工夫をしています。ぜひ楽しみにしていただければと思います。
ところで、先週(10/13)フロイト関係の最近の本などをインターネットで調べたり、購入の手続きをしているときに、本ホームページがGoogleの検索に登録されていたことに気づきました。
登録の申し込みをしたのは5月30日でしたから、約4か月半かかっています。
「心のナビゲーション」「心ナビ」「こころ楽楽」で検索をすれば、本HPがでてきます。
YAHOO!やinfoseek(楽天)にも、検索の登録を申請したので調べたら、登録はまだでした。
しかし、さきほど[10/17(月)]念のために両方を調べてみたら、YAHOO!の検索にも登録されていました。
2社の検索に登録されたのであれば、他のものにも登録されているのかもしれないと思い、調べてみると、MSN、Fresh EYEに登録されていました。
goo、BIGLOBE、Exciteなどにはまだでしたが、4つに登録されたので、そのうちに登録されるのかもしれません。
いずれにしても、ここ数年でブログに限らず、ホームページの数も急激に増えているようですので、新規のHPが登録されるのには時間がかかるようです。
今後、多くの人に本HPを読んでいただける可能性がでてきたような気がしますが、1年間くらいは実験期間、次の段階への準備期間として、まずは 『マンガ フロイト』の文庫化や単行本を書き上げることを主にして、少しずつスピードアップして、効果的に連動ができればと思っています。
それまでは更新のインターバルが長いかもしれませんが、「三日坊主」ではなく、「やる気」は十分にありますので、今後ともご愛読のほど、よろしくお願いいたします。
9月13日(火)
先週、ある若い人からいただいたメールの中に、‘「デジタル世代の若い人にも」と書いてあった通り、読みやすい易しい言葉で書いてあって、すらすら読めました。更新楽しみにしています。フランクル、アドラー、エリクソンの著作も読んでみたくなりました’とあり、嬉しく思いました。
また、「アナログ世代」や両刀使いの「中間の世代」の方も、更新のたびに読んでくださっているようで、感謝しています。
「更新」のスピードが遅くなっていて、申しわけありません。
そろそろ単行本の執筆のスピードアップをしなければと思い、それらの作業などをしていました。
単行本で考えていた「切り口」をホームページで展開しましたので、別の「切り口」の本にしたほうが良いと思い、再検討をしていました。その構成案が固まり、その「流れ(ラフプロット)」もつくっていました。
あとは各巨人の著作などで、彼らの生き方、理論、療法、症例、「真意」などを再チェックしながら、コツコツと書き続けて、推敲を繰り返していく段階に入りました。
HPと単行本をそれぞれ独立して読んでいただいてもわかりますが、それぞれが「補完」しあって、5巨人の「いいとこ取り」にいっそう役立つことができるようにしたいと思っています。
HPの更新と本の執筆が並行してできれば、彼らの「急所」を正確で簡潔な内容にして「更新」できますので、少々お待ちください。
また先週は、ある出版社のベストセラーの本を何冊もつくられている編集者の方と、久しぶりにお会いしました。
細山の現在書いている原稿を、他社ではなく「うちに持ってきて」と、おっしゃってくださいました。
そして、細山が以前に手がけたことのある別のジャンルの本についても、依頼してくださいました。
具体的にまだ公表できないのが残念ですが、面白いホームページをつくることにも役立ちますし、ぜひ早く現実化して公表ができるようになればと思っています。
そのためにも、本などの資料や部屋の整理、約15年間使っていた旧式のパソコンの整理・処分などをして、能率的にこなす必要がありますが、できるだけ早くHPの「更新」をし続けながら、実現化したいと思っています。
それと、もっとデザインなどのビジュアル面の工夫をできる時間が取れればよいのですが、しばらくは難しいようです。当面は、「中身」を発信できればよしとせざるを得ません。
各ページの原稿がもう少し多くなり、仕事が一段落した段階で構成を、大幅に(?)変えられればと思っています。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
8月30日(火)
昨日、日本テレビの「スーパーテレビ」(22:00~22:54)、「実録・多重人格の妻 体に居座る27の別人」を見ました。
3年前から取材をしてきたようで、以前にも同番組を見た記憶があります。このときは多重人格の現象・症状を、「人間には、こうしたこともあるのか!」という驚きの目で描いていたように思いますが、今回は妻の人格がほぼ統合をされてきた段階で、感動的で嬉しく思いました。
多重人格は、幼児期に繰り返し受けた性的虐待から、自分を守るために生じる心理現象です。6年前に、夫(62歳、イラストレーター)は妻(51歳)が多重人格であることに気づいたようです。
セラピストも指摘していましたが、夫の「安心感を与えるようにしている」という信頼される優しい対応が、彼女の人格の統合に役立っていると思いました。
番組を見ながら、細山の『「男と女」の関係の10段階説』の8段階、相手のトラウマを治せる愛(慈悲)のある「和合」をしつつある夫婦であると思いました。
また、妻に近い人格(15歳くらい?)が自分の不幸な人生を嘆くのではなく、映像化されることによって、「不幸だったけれど、今でも不幸な人のために、自分のことが役立つのね」というシーンをみて、彼女が治ることを確信しました。
なぜなら、彼女はフランクルのいう自分の「人生の意味」に気づいたからです。
この夫婦の体験は、単行本になる価値があると感じました。
細山は2,3年前に、ある月刊マンガ雑誌で、多重人格者の「人格の統合」を描く企画を始めたことがあるのですが、原作者(細山)、編集者、漫画家さんの連携プレーがまったくうまくいかず、見事にコケて、連載が4回で打ち切りになりました。その記憶(トラウマ!?)が、番組を見終わってから甦りました。
いつか機が熟したときに、企画が実現できて、わが「トラウマ(?)」が治ればいいなと思いました…。
8月15日(月)
8月9日、大学の同じ学科の友だち、荻原、作田、竹間くんと飲んで、暑気払いをしました。
化学科卒業のため、ほとんどの友だちは科学技術関係の会社や組織に勤めていますが、竹間くんと細山のみがマスコミ関係の仕事をしています。
竹間忠夫くんは自動車専門誌、経済誌、週刊誌の記者をして、15年前からフリーの経済ジャーナリストとして活躍しています。
彼の最近の活躍は特にいちじるしく、昨年7月に『101人の起業物語』(大宮知信共著、光文社)、今年3月に『夢のスーパーハイビジョンに挑む』(NHK出版)、6月に『サッポロビール
ドラフトワン革命』(実業之日本社)を著しました。
今年3月に竹間くんと飲んだとき、今後は新聞や雑誌の仕事は断わり、「ブックライターに徹したい」、そして書く際には「10万部を目指している」と話していました。
彼は新聞で連載記事を書いていたので、もったいない話だなと思いながらも、彼なりに状況判断をして決意したのだと思いました。
「10万部を目指している」という彼の考えには、特に共感を覚えました。
なぜなら、細山も秘かに「10万部を超える本を書く」こと、あるいは原作、編集することを目標にして、現実化することが大切だと思っていたからです。
どこの出版社でも初版部数を減らしていますので、出版されただけでは割に合わない場合が多く、「喜びも半ば」で、重版されて初めて企画が成功したといえ、プラスの「印税」も入り、喜びが増します。
同じ本が1万部売れるのと、10万部売れるのでは収入の額がケタ1つ違ってきます。
そうなってこそ「書き手冥利に尽きる」といえます。
たまたま本が売れるということもあるのかもしれませんが、細山の経験では、書き手、編集者、デザイナー、営業、広告などの関係者が、それぞれの能力を十分に発揮して、連携プレーがうまくいった場合には売れますが、それぞれの能力が発揮されずに、関係がギクシャクしたりして連携プレーがうまくいかなかった場合には、結果も思わしくないというのが実感です。
そのためには、まず「書き手」が、熱きパッション(情熱)、意思、夢をもつことが、現実化する上で非常に大切であると思っていたからです。
これは、なにも出版関係の仕事に限ったことではなく、竹間くんが書かれた、それぞれの業界にも共通して言えることのようで、まず1人の「やる気のあるキーマン」が出る必要があると思います。
『101人の起業物語』(光文社)は日本のIT革命を担う若手の企業家を扱った内容で、出版された時期もタイムリーでした。昨年の夏ころからプロ野球球団(パリーグ)の買収問題で、ホリエモンこと、堀江貴文ライブドア社長や、楽天の三喜谷浩史社長などが、「時の人」になり始めていたときでしたから。
細山も新聞広告を見て、全体が見渡せるとともに、どんな人間が成功をしているのかを具体的に知るのに便利な本であると思いました。2,3週間後くらいに、飯田橋の書店に行ったところ、平台に2冊だけあり、その1冊を買い、確実に増刷されるなと感じて、彼に電話をしました。
IT関連企業は、かつては「ベンチャー企業」として脇役的に見られていましたが、現在では「基幹企業(産業)」として社会のなかで大きな役割を果たし、社会を確実に変革しているというのが、細山の実感です。
現在5刷で3万部とのことです。ヒョッとすると10万部いく可能性も出てきているようにも感じますが……。
われわれの口コミの応援次第かもしれません(!?)。ぜひ、書店で下記の2冊も含めて、ご覧をいただき、買っていただければと思います(美しい友情!!)。自分の部屋・本棚に「積んどく」だけでも価値があります(言いすぎ!?)。
『夢のスーパーハイビジョンに挑む』(NHK出版)は、愛知万博で現在展示されているNHKの世界で最大のスーパーハイビジョンとコンテンツ(番組ソフト)の開発物語です。まさにNHK自身の「プロジェクトX」です。
ハイビジョンは走査線の数が1000本であるのに対して、スーパーハイビジョンは走査線が4000本という超高精細映像であるとのことです。
NHK,NHK技研や関係者、60人近くを取材して、テレビや映像関係者だけではなく、ビジネスマンが商品開発や問題解決のときに、ヒントが得られる内容となっています。
ところで、NHKの受信料不払い者の人数がだいぶ増えているようですが、NHKの経営者や社員が、視聴者の信頼をどう取り戻し、これからの「デジタル社会」にふさわしい組織にどう再構築するのかについての「プロジェクトX」の本が書かれてもよいように思います。
ぜひ、竹間くんに書いていただければと思いますが、いかがでしょうか?
ビール業界では「第3のビール」の開発・販売競争が激しいようですので、『サッポロビール ドラフトワン革命』(実業之日本社)もタイムリーな本であると思います。すでに2刷になったとのことです。
「ドラフトワン」は麦芽や麦を使わずに、大豆などをベースにした低アルコール飲料で、若い人の味覚にマッチする「スッキリ味」の飲み物を開発しようとした一人の技術者の発想に始まったという。
50人を超える関係者に取材をし、単に商品開発にとどまらずに、サッポロビールという会社自体が変わっていく様子を「生きた人間ドラマ」として描き出しています。
大学卒業後の竹間くんとの「再会」は、彼が「週刊現代」(講談社)の記者をしていたときで、23年くらい前になります。
作田くんと同じ会社にいた高橋くんの妹さんが勤めていた自動車会社へ、竹間くんが取材に行ったことから、情報が逆に伝わり、細山が「週刊現代」の編集部に電話をして再会をはたしました。
それまでマスコミ関係で、同じ学科に限らず、同じ大学の人とは、ほとんど出会っていませんでしたので、「懐かしさ」もヒトシオでした。
細山とは関心のあるジャンルが異なり、人生観などは対極にあるように思いますが、プロの「ブックライター」としての竹間くんの今後の活躍を、ますます期待したいと思っています。
そして、彼の「書き手」としての良い点を見習わせていただこうと思っています。
「10万部」、お互いに実現しましょう! そして、1冊だけといわずに、2冊、3冊、……、といきたいものですね。
夢は大きいほうがよいですし、心を明るくしてくれて、心理学的な効果もあるようですので……。
8月1日(月)
先月下旬は、細山の「個人史」にとって、二つの大きなことがありました。
その一つは、20代のときに禅寺へ一緒に坐禅をしに行った藤野さんと7月20日、約23年ぶりに東京で会ったことです。
藤野さんは、大学の一年先輩で数学科を卒業した後、哲学の大学院に進み、都立高校の教員をされていましたが、本当に出家をして、専門道場の寺(曹洞宗)などで修行をし、5年前に禅寺の住職になりました。
細山同様、サラリーマン家庭の出身ですので、大変だったと思いますが、立派であると思います。
親が住職であれば、「資格(僧籍)を取るための行」をして、世襲的にお寺を継ぐことができますが、在家出身の人間がお寺の住職になるためには、婿養子になったり、師匠に本当に認められなければなれないからです。藤野さんは後者です。
お元気そうで、年月のブランクをぜんぜん感じずに、しばらくぶりに禅の話などができて大変に楽しい時間でした。また、機会を見てお会いすることになりました。
細山は20代のとき、寺で本格的な修行をしようかと迷ったことがありましたが、『禅語録』を読んでいるときに「歩歩是道場」という言葉に出会い、やめました。
言葉の意味は、自分の歩む一歩一歩が、「いま、ここ」が修行の場であるということです。出家しなくても在家のままで修行ができると解釈したわけです(師についてするのが禅の正式な修行法です)。
独学ではあるものの、最近、自分なりの「気づき」があり、社会の中で表現して実現できればと思っています。
前回の本「日記」(7/4)に書いた、もう一つのしたいページとは、「普遍的無意識にいたる道(仮)」ということで、深層心理学と宗教の関係を書いてみたいと思っています。
一般的には「宗教」というと「迷信」・「マヤカシ」的なイメージで見られたり、「抹香臭いもの」「ご利益を得るもの」と考えられていたり、「真の宗教」との出会いがありそうでないのが現実です。
「ニセモノの宗教」あるいは団体が多いのは事実ですが、「ホンモノの宗教」が「普遍的無意識」にいたることに役立つことを明らかにできればと思っています。
禅は心理療法(サイコセラピー)としても、高く評価されていますし、深層心理学とも関係があります。
その新しいページ(来年以降)の中で、禅のことも書きたいと思っていましたので、藤野さんとの「再会」はタイミングのよいものであったようにも思います。
もう一つのことは、細山が描き下ろしのマンガ本をつくったり、現在の仕事でも、大変にお世話になっていた双葉社の地引功一さんが、定年を迎えられて、7月25日に「送る会」のパーティーがあったことです。
社員の方々を中心にしたパーティーでしたが、予想を超える出席者数になり盛会でした。その後、2次会、3次会、4次会があり、朝の5時にお開きになりました。いずれも思い出に残る楽しい会でした。
地引さんとは、ほぼ20年前に出会い、その約2年後に『マンガ ユング 深層心理学入門』をつくるときに漫画家さんを紹介していただいたり、ネーム(コマ割りと吹き出しのセリフなど)を徹夜で見ていただいたりしました。
その後、『マンガ ホーキング』など、14冊くらいの本で同様にお世話になりました。
いずれも、お礼は薄謝でボランティア的でしたが、気持ちよく協力をしてくださいました。
地引さんは人間好きで、その人脈の広さと好奇心の旺盛さ、行動力などに助けられました。
地引さんは「漫画編集一筋、37年4か月」という大ベテランで、 「スーパーアクション」の編集長などをされて、多くの漫画家さんの才能を伸ばされました。特に、星野之宣(『2001夜物語』など)、諸星大二郎(『西遊妖猿伝』など)、花輪和一(『護法童子』など、最近の話題作に『刑務所の中』青林工藝舎)さんなどとも仕事をして、現在でも親しくされています。双葉社の「生き字引」的な存在であったようです。
最近の約7年間は、成人マンガの単行本化を主に担当されて、双葉社系の「エンジェル出版」を軌道に乗せられました。
本来は「優秀なインテリ」なのですが、それを表面に出さずに、いわば「俗」に徹して仕事をされて、しっかりとしたマンガの編集技術を持ったプロ中の「プロの編集者」でした(す?)。
「能ある鷹は爪を隠す」という言葉の通りでした。いや「爪」を隠しすぎたような気がします……。
いずれにしても、細山の恩人であり、「わが菩薩」の一人であると思っています。大変、お世話になり有難うございました。また、大変にお疲れ様でした。
でも、まだ「今生の別れ」というわけではなく、また一緒に仕事ができるようになればいいなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
まだ具体的に決まっていないのが、残念ですが……。細山に、もう少し能力と行動力があればよいのですが、たりなくて申しわけありません。今後、少しでも「恩返し」ができればと思っています。
まだ、地引さんの持っている編集技術や考え方を学びきれていませんし、お互いのためだけではなくて、縁のある人、出版社・会社、読者に楽しんでいただけるように、役に立てれば…、と思っています。
しばらくは、お母さんの看病・介護をしながらも、お身体を休めてください。また、今まで自分を押し殺して、仕事をされてきた面があるような気もしますので、これからは地引さんが隠されていた「爪(才能)」をあらわし、「自分はこれをしたい! やりたい!」と思うことを優先して、されるのがよいのかもしれません。
それが、老け込まずに、若さ、元気を保つためにも必要な気がしますが、いかがでしょうか?
以上、一見、無関係なお二人のことを書きながら、思いついた言葉があります。
それは、「聖と俗」「煩悩即菩提(悟り、発心)」という言葉です。
後者の意味・解釈はいろいろあるかもしれませんが、「煩悩と菩提が別物ではなく、表裏一体である」、あるいは「煩悩の中に菩提があり、菩提の中に煩悩がある」ということです。つまり、「俗即聖」といえるかと思います。
藤野さんからいただいた名刺の裏やご自坊を紹介した小冊子には、「すべてのものは、すでに救われている」という言葉が書かれていましたが、上記の2つを含み、差別、分け隔てのない深い事実・境地を表現されているように思いました。
お二人のご希望、同意があれば、機会をみて、いつか3人で一緒にお会いして食事でもと思っています。
いずれにしても、お二人のことは細山にとって象徴的なことで、「聖(生、性を含めて)と俗」「煩悩即菩提」に関係することを、仕事としても表現し、統合をしながら少しでも究めて、自他ともに「心身ともに豊かになる」のが、これからの細山の「テーマ、課題、役割」であると思っています……。
7月4日(月)
早いもので本ホームページを立ち上げて、1か月以上が過ぎました。
身近な人がリンクしてくれたり、リンクを依頼されましたので、先日「リンク、リンク、リンク」のページをつくりました。つくりながら、相互リンクすることで「人との出会い」が生まれると思い、希望する人を募る文章を入れてみました。
少しでもHPの内容と情報を必要としている人に見てもらえるように、お互いに役立てればと思ったからです。
検索サイト(Google,infoseek,Yahoo! JAPAN)に登録の手続きをしてから、ちょうど1か月がたちました。インプレスのマニュアル本『できるホームページ・ビルダーV9』によれば、「1週間から1ケ月の時間がかかることもあります」「登録するときにホームページの審査が行われ、審査に合格したものだけが登録されるようになっています」とのことです(120,121頁)。
すでに本HPは登録手続きをして1ヶ月が過ぎました。審査に「不合格」だったのか、不合格の場合、連絡がくるのか、わかりません。本当の実状や審査の基準は何なんでしょうかね?
ある人によれば、続けていると、自然に用語などが、検索サイトに引っかかるようになるとのことで、気にしなくても良いとのことでした。
でも、不特定多数の人に読んでいただける確率が高まるので、検索サイトに登録されればいいな、と思っています。他の人の推薦があれば、登録される場合があるとのこと。もし、不合格の場合、どなたか、よろしくお願いいたします。
もし、推薦をしていただいた場合には、メールをいただければ幸いです。
いずれにしても、今はあまり反応の広がりを気にしすぎずに、したいこと、しなければいけないことを、こなすことが必要かと思っています。なかなかこなせませんが……。
ナビ1「心を楽にしてくれる考え方」の第4回の原稿「5人の深層心理学者について」がやっと書けました。
今後、推敲や加筆もしたいので、ナビ3「5人の深層心理学者について」という新しいページを起こして入れました。
これで、やっと「骨格」がほぼ出来上がったように思います。本当はまだしたいページもあるのですが、それは今の各ページの目途がついてからにしたいと思っています。
ホームページの効用については、後で落ち着いて考えてみたいと思っていますが、つくることによって、自分の「心の空間」がまず広がるような気がします。また、いままで会話や縁がなかった人との話題やパイプとしても役立ち始めています。
ある意味では、内容や形式は何でもいいわけで、まだまだ可能性のある新しい「媒体」「コミュニケーション手段」だと思っています。
つくるのは結構、大変な面もありますが、喜びがあり、まだつくられていない方には、ぜひご自分でつくってみられることを、お薦めします。それが、いまの感想の一つです。一昨日、高校時代の友達に半年ぶりに会って飲んだので、薦めたのですが……。
6月6日(月)
今年も自殺者の統計が発表されました。多少減少したものの7年連続で3万人を越えるという異常事態が続いています。
今回、「プロフィール」の第3回目に書きましたように、友達の自殺や姉の死は小生に精神的なショックを与えました。現代の心理学の専門用語で言えば、PTSD(外傷後ストレス障害)になっていたといえるかもしれません。
この自殺や死の問題を自分なりに解決できたのは、20代が終わるころでした。それは、坐禅をしたり、仏教のお経、特に『法華経』の「常不軽菩薩品」などを読んでいたときに、あらゆる現象は自分にとっては「菩薩の現われ」、つまり友達や姉は自分に死や生命の意味を、命をかけて教えてくれた「菩薩」だったと解釈できて、それぞれに感謝したときに、心が楽になりました。
作家・吉川英治の言葉に「われ以外、みな我が師なり」という言葉がありますが、これを発展させて、「万象万人、みな我が菩薩なり」と自分なりに表現しました。
フランクルが言っているように、不幸な体験のなかに、まさに「意味」があり、それを自分なりに発見したときに、心が楽になったのです。
いつの日にか、自殺願望をもっている人にも本ホームページを見てもらえて、生き続けることに役立てればと思っています…。そして、その人からメールをもらえることができれば、それに勝る喜びはないといえるかもしれません。
そのとき、自分を苦しみから救ってくれた仏教や深層心理学への「恩返し」の一つができたといえるからです。
そのためにも、目の肥えた人からは「ド素人」(チガイナイ!のですが)のものにみえる(らしい)本ホームページを(ソフト「ホームページ・ビルダーV9」を使っている細山自身は、さまざまな色や書体、パターンが出るのが嬉しくて、単行本的な統一感より、「雑誌的な不統一感」を楽しんでいるのですが…)、多くの人に見て喜んでいただき、見ただけでもホットして、心安らぐものにするために、早く「入門編」のデザインを、「初級」の段階にレベルアップしていきたいと思っています。
7月初旬を目標にして、工夫をして変えてみようと思っています。完成度の高い、カッチリできたホームページが多いなかでも(?)、手作り感のある独自のスタイルのものにできればと思っています。
6月1日(水)
本ホームページを立ち上げたことをメールでお知らせしたところ,ほとんどの方が、見てくださり、ご返事をいただきました。ありがとうございました!
辛口の感想から、「シンプルでコンセプトがストレートに伝わってくる、わかりやすいサイトに仕上がっていますね」という、嬉しくなり涙が出る(?)ような愛情のある(!?)感想まで、いろいろといただきました。
でも、すべてのご感想に感謝しています。その真意を分析して、すべて本ホームページの改善に生かしていきたいと思っていますので…。
辛口、甘口、オールOKですので、遠慮をされずに、ご感想、ご意見をお寄せください。
また、文字だけではなく、絵や写真などの映像も入れたほうがよい、見出しの書体やバックの色使いなど、もっと統一感を出すように工夫をしたほうがよいなど、いろいろなアドバイスをいただきました。
いままでのところ、まず何を伝えたいのかという内容と、送信までに早くたどり着くことに力を注ぐことに手一杯でした(言いわけ?)。
目次ページの項目や「トップページに戻る」という文字が、赤字に戻らない、プリントアウトすると文字が崩れるなどの問題がありますが、これらも解決したいと思っています。今回は、更新予定日を守ることを優先いたしました。
パソコンのソフトを使いこなすには、時間がかかりますが、これから、技術力と能力をアップして、改善をしていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします!!
5月25日(水)
イヤ~~、けっこう大変でした!
でも、おかげさまで、やっと立ち上げることができました!!
新しいパソコンを購入して約3か月半、ホームページをつくり始めて約2か月半かかりました。
非力ですが、あえて大胆な(!?)ホームページに挑戦をしてみました。
まだまだ不十分のところが多いのですが、まずは立ち上げてテストすることを優先しました。
パソコンの導入からソフト、ホームページのことまでを教えてくれた岡野夫妻、ホームページ案をみてくれた千崎さん、作田くん、地引さん、古沢さん、刺激を与えてくれた本多さん、パソコンやソフトのことなどをいろいろと教えてくださった田端さんなどに感謝します。(ここに苗字を入れると、まずい方はメールで教えてください)
ソフトをまだ十分に使いこなせず、技術と能力がともなっていませんので、実現できていないところがありますが、ご了解ください。入っていれば良しとして、今後の課題としました。
たとえば、一番大きな問題は「体験談」を「掲示板」の形式にするのがよいのか、どうかということです。
デザインや色の使い方については、創作マンダラを描いている前田常作さんの絵が好きなので、いろいろな色を使いながらも、見て読んでくださる方の心が安らぐような色使いやデザインの「美しい」ホームページになればという願望をもっていますが…。
上記の件をご理解いただき、よきアドバイスをいただければ幸いです。
本ホームページを、「急がず、無理をせず」にコツコツと作っていきたいと思っています。
多くの人々のお役に立てれば嬉しいですが、まずは少数だとしても、悩んでいる人のために、少しでも確実に役立つものにできれば…、と思っています。
応援のほど、よろしくお願いをいたします!!
ナビ9 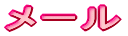
rakuraku@dream.com
本ホームページについてのご感想、ご意見をお寄せください。
また、情報や質問など、何でも結構です。
トップページに戻る


